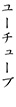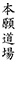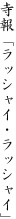『通信』「長仁寺報」 一覧 ≫ 常照『通信』
常照『通信』

- 今年も残すところ一カ月となりました。如来さまの船に乗せられて嵐の中を如来さまに操(あやつ)られてあっという間に来たと、同時に五年、十年が過ぎた感じもするのです。なぜなら生長させられたからです。この一年間に通信のほかに、五冊の冊子が出版され、ユーチューブや月四回のリモート法座、外へ出かけるご縁など、よくもこれだけの事ができたと驚いています。これも同朋の皆様のご尽力あっての事、背後に如来さまのご本願力のお陰であります。
先日、久々にゆっくりした時間が与えられたので法喜と朝の散歩に近所の公園へ出かけました。湖面に紅葉がきれいに映っています。一句浮かびました。
光受け 増々(ますます)映(は)える 紅葉(もみじ)かな
草人(そうじん)
さて、この頃気になるニュースがあります。若者のあいだでせき止めなどの市販(しはん)薬を過剰に摂取して「オーバードーズ」という興奮状態になることが流行っているとのことです。現実逃避とか、経済的苦しみから一時的に逃れるため、死にたくないからしているとか。色々あるようです。解説者などは現代の多くの人が未来に希望が持てず、結婚に対しても消極的となり、子育ても困難である。「生まれなければよかった」という声が上がっているとのことです。政治や教育などあらゆる分野でそのことが問われているのに明るい方向が見えて来ないという意見がありました。
また、あと二年後には日本だけで七百万人の認知症状の人が出るとの予測がでています。世界で起こっている紛争や戦争、自然災害、暗くなるニュースが毎日飛び交っています。老いも若きも何ともやりきれない環境の中で逃げることも出来ずに日暮(ひぐらし)をされている人が多いのではないでしょうか。
高度経済成長のなか田舎から都会へ就職された人たちの心のよりどころとして新興宗教が流行りました。ほとんどの教えは先祖供養や右肩上がりの希望を与えられるような教義です。それも経済成長が弱まり、教義も形式化したり政治に近づいたりして魅力を失いつつあります。また、法外なお金を搾取する教団も問題となっています。相談できる良き先生や友達もいないために引きこもりやうつ病、さらには自殺者も増えています。こうした中で頭が下がっていく他力の教えは生活の中でいかなる救いをもたらすのか。強く願われ、問われています。
この前、ある少年との嬉しい出遇いがありました。「形の無い本当の光は暗い影の形のところにこそ生きて現れている。だからいつもつきまとっていたことを知らされ驚きました」私と一時間の会話をした後の感想文です。一カ月前、彼とのやり取りの中でさっと顔が明るくなったのが印象的でした。感想文を読ませて頂き目頭が熱くなりました。改めて機(き)の深(じん)信(しん)他力(仏から照らされた私の姿)の歌のお心が味わえて来ました。
松影(かげ)の 暗きは月の 光かな
私自身が本願に帰依するまで、自分から自分を見ては裁き、苦しみました。ですから親鸞さまの「悲しきかな、愚禿鸞(ぐとくらん)」という悲しい中にも明るい世界があることは長い間、知識として知っていても味わえませんでした。懺悔(さんげ)の裏に報謝あり、報謝の裏に懺悔あり。暗い影は如来の光明のお照らしのお陰であります。悪人の救いであります。全く逆の受け止め方をしていたのですから苦しかったのです。
私が高校生の頃でしょうか。父が泥酔の中で「不連続の連続」という言葉を発しました。妙にそのお言葉は心に残りました。父が勉強する姿を見たことはありませんでしたが「樹心の会」というグループの仲間に入れて頂き酒を飲むことを楽しみにしていました。藤代(ふじしろ)聡麿(としまろ)先生のご法話を聞いていました。父の宿業を照らしたお言葉だったのでしょうか。
娑婆と浄土はこちらからは不連続です。しかし、浄土から見たらつながっています。浄土からのおはたらきのご廻向のゆえに連続です。如から来生です。「不連続の連続」です。今、あの声は如来さまが父の口を借りて私への呼びかけであったのかと知らされます。六道輪廻の三界(欲界、色界、無色界)を超えた世界に太陽が昇る。すなわち本願に帰依されるとおのずと生命が明るく元気になり、風景がひろがり、それまで見えなかった世界が見えて来ます。
「南無とは帰命、すなわち発願廻向のこころなり、阿弥陀仏というはその行なり」蓮如上人のお文さまには何度も出て来るお言葉です。「阿弥陀仏というはその行なり」どんな行なのか。疑問を持ち続けていましたが明らかになって来ました。自分ばかりをたのんで如来の本願を疑い信ぜず、たのまず反抗していたのです。自分には真実はなく、汚れ、清浄の心は無いのです。如来は曠劫(こうごう)以来(いらい)、一念一(いちねんいち)刹那(せつな)も清浄であり、真実であり続けて私に付きまとって下さっていたのです。しかし、自分にも多少でも良いところがあると自己肯定してその自分を認めてもらおうとしているときは如来様をなきものにしているのです。この事に気づかされるのは大変なことです。「薄紙一枚がはっきりしない」と本物の同行さんが苦しまれた壁です。私においては大石先生がビニールを通してしか見えない。見えるのだけれども見えない。と二十四年間かかりました。自我の頭が下がるまで、すなわち帰命するまで如来さまがご修行し続けて下さっていたのです。二十年三十年どころではありません。
五十六億七千万
弥勒菩薩はとしをへん
真実(まこと)の信心うる人は
このたびさとりをひらくべし
これから五十六億七千万年先ではありません。すでに過ぎて来たのです。阿弥陀如来に帰依するために阿弥陀如来がご修行、ご思案して下さり続けて来たのです。私どもはすぐに諦(あきら)めますが如来は片時も諦めず、見放さずに私の煩悩に付き添い給うて、影の如くに寄り添い給うて来られたのです。私がいくら反抗しようと、逃げようと、ごまかそうと忘れようと
如来大悲の恩徳は
身を粉にしても報ずべし
師主知識の恩徳も
骨をくだきても謝すべし
身を粉にしても、骨を砕いても私が如来に帰依するまでご修行してこられ、今もこれからもおはたらきづめであります。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。
私が帰依するまで如来さまが先に私の宿業、煩悩に帰依して下さっていたのです。如来さまの利他行、還相回向(さとりの世界から、迷いの衆生を救うために下がってくださる)です。如来さまが私と一体と成り、心に口に南無阿弥陀仏と現れて下さっていたのです。
しかし、そのお心は帰依されるまでわかりません。曽我量深先生が
如来、我と成りて我を救い給う
されど我は如来に非ず
炭に火が点かないと、明るくなったり、温かくなったりしません。火が点いた時は炭と火は一体です。しかし、炭は火ではありません。炭を離れて火はありません。炭は火が点くためにあったのです。磁石と釘のお譬(たと)えや接ぎ木のお譬えも同じです。仏(ぶつ)・凡(ぼん)(凡夫)一体(いったい)。機法(きほう)一体(いったい)。宿業と本願。私を離れて如来無し、如来さま離れて私無し。親子同時誕生です。二にして一。一にして二の世界です。そこから不思議に人の幸せを願う心が動き出します。そんなことは微塵もない私の心に動き出すのです。
仏教は苦悩する人に何を与えているのか。清沢先生は「内観(止観)」であるといわれたそうです。心理分析やカウセリングと似ているようで違います。人間が人間を分析しても明るくはなりません。私がそうでした。
「浄土論註」には止観(しかん)(内観)の事を静かな寂静(じゃくじょう)三昧(さんまい)と清浄なる浄土を観察する心として説かれています。大石先生は味わいとか響きを大事にされました。仏法の味わいを「浄土論註」では
仏の国土を観(み)てその清浄さにふれる味(み)楽(らく)
一切の衆生を大乗(どんな人も救われる)に入れて一筋に生かしめる味楽
衆生にいつまでも功徳(仏の功徳)をたもたせ仏道から退転するような虚(むな)しい行為をさせぬ味楽
衆生の種類に応じて救済し、仏を供養し、自ら願ってあらゆる世界を仏の国土とする味楽
他力廻向の信心の世界から幸福感や充実感が自然に沸いてきます。平凡な生活の中や人間関係の中に浄土の味わいが出て来るのです。仏法の世界を知らず、食わず嫌いでいたことに気づかされた人は幸いです。もっと早く知ればよかったと何度も言われていた教育長さんがご門徒におられました。現代の暗記力、理解力が中心で心の世界がお留守にして来たつけがあらゆるところに出てきております。でも、簡単に文部行政は変えられないそうです。
私は生活の中で内観のお陰で大いに助けられています。例えば、自分と意見の違う人の話を聞いている時、以前の私だったら黙していても腹の中では相手の話の内容を批判、否定してばかりしていました。そこには余裕がなく相手の立場や業は見えていません。腹の中で鉄砲を撃ちまくっていたのです。打ち方止(や)めとの号令(南無阿弥陀仏)でこちらからの世界が止まったら、向こうからの世界がはじまります。目の前に花が咲いていた。鳥が鳴いていた。青空が広がっていた。支えて下さる方々がおる。
「なんだ、こんなに恵まれて素晴らしい中にいたのか。如来さまを知らなかった。すでに宝の山の中に在った」。これはアジャセ王の廻(え)心(しん)に通じています。
アジャセ王は世尊に申し上げた。世尊よ、私は世間を見渡しますに、伊(い)蘭(らん)という毒の樹から
伊蘭の樹が生えます。伊蘭の実から栴檀(せんだん)の樹(かぐわしい香りの樹)の生えたことを見たことはありません。しかるに今、私は初めて伊蘭の実から栴檀の樹の生じたのを見ました。伊蘭の実というのは、私のことであります。栴檀の樹というのは、私の心に生れた私に根のない如来廻向(えこう)の他力の信心のことであります。
根のないというのは、私は今まで、恭(うやうや)しく、謹んで如来に事(つか)え奉(たてま)つったこともなく、法宝僧宝を信じたこともない者でありますが、こういう者へ、この信心の生じて下されたのは、如来の廻向のお陰であります。世尊、もし私にして、如来世尊にお遇いすることができなかったらば、わたしは無量永劫の間、地獄へ落ちて限りのない大苦悩を受けなければならぬのでありました。私は現に仏を拝したてまつっていますが、願わくば、この見仏のあらゆる功徳をもって、未来の衆生の救われることを願います。
教行信証の信巻 聖典265頁
大石先生が接ぎ木のお譬(たと)えをされたことがあります。私は嬉しくてお説教でそのことをお話し
ました。しかし、その時は受け売りでした。身の事実とは成っていませんでした。
今ようやく芽が出て樹や枝が生長を初めています。ご本願が私の宿業を使って下さり宿業が明るくなりました。寺生まれでよかった。あの両親がいてくればこそ、子供たちのお陰です。一切のお陰であります。ご恩の中の生活です。
元気で一刻も早いうちに気づいてほしいのが親(如来)さまの願いなのです。しかし、何か理由もなく反抗してしまいます。自分でも気づかない自我がはたらいているのです。深い聞法がないとそのことに気づけません。
親を求めて親に遇えず、生まれ故郷に帰りたくて帰れず。安心できずさ迷い続けて来た私がよき師に出遇い、よき朋(とも)に出遇い。真実の親様、如来に出遇うことが出来たのです。これほど幸福なこと、安心なことはありません。
大無量寿経の下巻の終わりころに、すでにみな浄土の中にありながら、偽の浄土の在り方、仮の浄土あり方、真実の浄土あり方の問題がでています。仏智を疑惑しているからだとあります。大石先生が「籠(かご)の扉はあいている。出なさい」と仰せられました。「そういわれてもどう出ていいのか。寺から出ることなのか。先生は自由だけど私はそうならない。無理なことをよく仰せられるな」と疑問と反抗心がよぎりました。自分の思いで作った籠(かご)があると思っていただけで、本来籠などなかったのです。自由な天地がすでに開かれていたのでした。
親鸞さまは広大なる十八願の天地の世界が開かれたところから、すでにその道を歩かれていた大先輩として七高僧さま方と出遇われ、さらに世尊、さらに弥陀の本願とさかのぼられて行かれたのではないでしょうか。大石先生が「本願は一番古くて、一番新しい」と仰せられたことはこのことだったのかと今、味わわされます。ご本願のおはたらきは常に新しいのです。宿業煩悩も常に新しいのです。
令和五年(2023)年十二月初旬
常照 拝


- 27日から29日にかけて長仁寺報恩講がつとまります。その準備の日々です。コロナのために三年間はお泊りがありませんでしたが、今年は新潟から渡辺義彦さん、岐阜から田中秀法さん、森はる美さんが泊まり込みでご来寺くださいます。自然に気が引き締まります。
これに先立ち、13日総代役員世話人会議がありました。本山からの一戸あたりの宗費や一年間の活動報告や会計報告、営繕のシロアリ対策等協議されました。私は住職を退(しりぞ)いていますので肩の荷が降り、気持ちが楽になったと思いながら端(はし)の席に座っていましたところ、最後に前住職挨拶の指名がありました。私は次のように挨拶をさせて頂きました。
このたびの地震被害を受けた、石川県、富山県地方は真宗の盛んな所です。知り合いの野崎さんとようやく電話がつながりました。「家は半壊しました。井戸があり、その点は助かっています」と。「無事でよかったです。蓮如上人の聞き書きの中で、寺が壊され、さすがの蓮如上人も意気消沈して行方をくらましたそうです。ようやく探し当てたお弟子の善(ぜん)従(じゅう)さんは『よかった、あなたがおられればご信心の力でまた建物はたてられる』。そしてその通りになったとのことです。お念仏しながら慌てずに一つ一つ復興してください」。「はい、みんなと協力して復興します」とのご返事が返ってきました。
「今晩の会議で話し合われたことの一切はご信心をいただくため、信心を後世に残していくためです」と申し上げました。皆さん引き締まった感じがしました。恩徳讃の歌声が力強く響いてきました。私自身ご信心の道を一筋に貫いていくように如来さまから励されたように感じました。
報恩講をお迎えすることに際して、改めて神妙な気持ちにさせられています。ここに『知恩』(円照寺・暁青発行)という冊子があります。その中に暁(あけ)烏(がらす)敏(はや)先生のご文章があります。
昭和二十一年の報恩講も近づいて来た。私は知友同行と共にこの報恩講を
迎うるのに胸を躍(おど)らしておる。報恩講に際して聖人に捧(ささ)ぐる
最上のお供え物は、聖人のお客人を迎うる事である。私は聖人のお客人と
して私の営む報恩講の御座(みざ)に一人でもたくさんの知友同行の集まら
れる事を望んでいるのである。聖人の最も喜ばせられるお客人として皆さ
んをご招待する光栄を感ずるのである。・・・・・・・・・
聖人は「如来大悲の恩徳は 身を粉にしても報ずべし、師主知識の恩徳も
骨をくだきても謝すべし」と記されてあります。如来さまから、このいの
ちよりも、もっと大事なもの(他力回向のご信心)を頂いておるのである
というお喜びのあふれであります。今日の私どもが報恩講をつとめさせて
頂くことは、聖人のこの如来知識にたいする感謝のお言葉を私どものもの
として聖人にたいしてお礼申すのでございます。この「如来大悲の恩徳は
身を粉にしても報ずべし」という聖人のお言葉を、私どもは毎日毎夜のお
礼の心として新しい年を迎えたいと思うのであります。
暁烏先生のご信心の躍動が響いてくるご文章です。この報恩の心がはたらいているからこそ、今年七百六十三回忌の御正忌報恩講がつとめられるのであります。真宗教団は報恩講を中心とした教団です。ところが七百五十年もたつと、形式化、習慣化されてその本質が見失われてしまいます。私自身がその中に在ることが照らされます。若い頃、何のために報恩講がなされているのかがぼやけていた時は準備でくたびれ、人間関係に疲れて親鸞さまのご影像の前で手をつかされ、申し訳なさに涙が出たことがありました。この度の準備等は現住職、坊守が主(おも)にしてくれたお陰で改めて本来のあり方が問われました。
先日、黒澤明監督の「生きる」という映画をテレビで視聴しました。お役所の課長さんが形式仕事の日々の中、余命六カ月の癌になったのです。昔はがん告知は本人に知らせませんでした。ところが主人公の渡辺さんは知ってしまったのです。三十年間欠勤もせず、遊びもせずひたすら真面目に働き続けたことが意味をなさなくなりました。貯金を下ろして遊びに行くのです。
遊び方が分からず、酒場で知り合った人に教えてもらって、キャバレー、パチンコ、ストリップ、若い女性と喫茶店に行く日々でした。しかし、心のむなしさは晴れるどころか増々むなしくなっていくのです。そのうち、若い女性から「やせて気持ち悪い」といわれます。「わしはもうすぐ死ぬ、何をしていいのかわからない。たのむから教えてくれ・・・・・。」しばらく沈黙のあと、女性が仕事で作っていたおもちゃを握りしめて帰りました。次の日から役所にもどり、陳情に来ても後回しにしていた仕事がありました。雨が降るとぬかるんでいた土地を公園にする仕事です。それから人が変わったように役所の壁を越え、妨害の圧力を越えて、仕事に取りくんで行きました。そして公園は出来上がりました。
渡辺さんは死んで、渡辺さんの遺影写真の前でのお通夜の席です。上司は自分たちがあの仕事をやったように自慢します。同僚は「なんであんなに地味な人があのような立派な仕事が出来たのだろう。もしかしたら、渡辺さんは癌を知っていたのではないか。そういえば・・・・・」それぞれ思い当たるところがありました。
最後に警察官が焼香にきます。「お詫びします。昨夜十一時ころ雪の中、公園のブランコに老人が乗ってゆっくりとゆれていました。注意しようと近づきましたが、何とも言えない美しいメロディーで『命短(いのちみじか)し恋せよ乙女(おとめ) 赤きくちびるあせぬまに 熱き血潮(ちしお)の冷えぬ間に 明日の月日は ないものを』(ゴンドラの唄)が聞こえました。そのときのお顔が赤ちゃんのように嬉しそうに、満足しきっておられたので、そのままそっと帰りました。あの時連れて帰ったらよかったのですが」父親が浮気をしていたと思っていた息子夫婦や同僚たちは皆沈黙です。
蜂屋賢喜代(はちやよしきよ)先生は「宗祖聖人を懐(おも)う」の中で
親鸞聖人はなすべきだけをなしたという満足をもって終わられておるので
あります。死なれたというよりは生き尽くされたというべきであります。
・・・・・本土に帰るという心地(ここち)であったのであります。それは
帰るべき時が来たから帰るのであって、帰るのは再び来たるべきことであ
ったのであります。それはひとえに如来本願の廻向であって、往相の廻向
も如来のたまものであり、還相の廻向も如来のたまものであります。それ
ゆえその身の幸(さち)を喜んでひとえに仏恩の深きことをいよいよ喜ばれ
たのであります。
と述べておられます。大石先生の死のお顔、お身体に接した時の私の受けた印象と同じであります。そういう生き方、死に方が第十八願の信心から恵まれるのです。人間からは決してできる事ではありません。
私は映画に引き込まれて、途中から涙が止まりませんでした。私と何か生き方が重なっていたからです。生死を超えた道があり、よき師、よき友に出遇(であ)えたことのご恩を感ぜずにはいられませんでした。余韻が後々まで残りました。
愛知県刈谷市の水本健太郎同行さんが医師から法座に行くことを止められた際に「あんたはあんたの医道という道があるやろ。わしは仏道という道がある。だから聞法に行って死んでもかまわんのや」。それを聞かれた医師は止められなかったそうです。法座に車いすで来られ、立ち上がった時の健太郎さんの崇高なお姿、ご尊顔は終生忘れられません。刈谷本願道場には健太郎さんの願いが生きています。
今年の報恩講に岐阜から来られる田中秀法さんも足はよろよろです。世間の医師の診断は認知症です。常識からはとても九州まで来れるはずがないのです。しかし、娘のはる美さんの付き添いもあって、刈谷本願道場、三重本願道場、高岡本願道場にご参詣されています。不思議にも仏法の会話はまったく問題ありません。いつ死んでも後悔のないご姿勢があります。だからそのままに認知症に臆することなく、明るく生かされていることが証明されています。
映画の話に戻ります。最後のシーンで日常生活にもどります。お通夜の酒の席で、「渡辺さんのように立派な使命感をもって仕事にとりくむぞ」。と意気込んだのはその場限りで、また業に負けて同じことをくり返しています。人間の愚かさがしみじみと伝わってきました。他人(ひと)のことではありません。第十八願の信心の世界が開かれないと新生活は展開されません。大石先生はそこを生涯貫いて見せて下さいました。親鸞さまのみ教えに
その廻心とは、日ごろ本願他力真宗を知らざる人、弥陀の智慧をたまわり
て、日ごろの心にては、往生かなうべからずとおもいて、もとのこころをひ
きかえて、本願をたのみまいらするをこそ、廻心とは申しそうらえ。
歎異抄第十六章
報恩講は日ごろのこころから、本願の世界へと一歩引き出される勝縁です。そこを逃(のが)しては無始よりの迷いから抜け出る御縁はありません。
無始(むし)流転(るてん)の苦をすてて
無上涅槃を期(ご)すること
如来二種の廻向(えこう)の
恩徳まことに謝しがたし
正像末和讃
娑婆(しゃば)永劫(ようごう)の苦をすてて
浄土(じょうど)無為(むい)を期(ご)すること
本師(ほんじ)釈迦のちからなり
長時(じょうじ)に慈恩を報ずべし
善導大師和讃
親鸞さまも釈尊も蓮如上人、先生方は娑婆永劫の苦から解放された救いを説いて下さっています。
先日、函館市の永田さんから本の注文を頂きました。ユーチューブを見られ、ホームページから本が出ている事を知られたそうです。お礼の電話でまたお互いに驚いたことがありました。永田さんは三十年まえに出版された『師との出遇いを確かめる』という冊子を読まれていたのです。その時の私の名前は忍です。髪も長髪でした。「まさか同一人物だとは思っていませんでした」と。「私は別人のように成らされました」と申し上げました。大石先生に遇い、お育てを受け、願いに生きる心が発起されたからです。自分でもわかります。自分のユーチューブを見ていて、これは私かなと思わされることがよくあります。もうひとつ正確にいうと、全く変わった面と全く変わらない面とがあります。
変わった面とは「浄土論註」に好堅樹(こうけんじゅ)のおたとえがあります。
地中で百年間、枝や葉をつけて、地上に出るや一日に高さ百丈生長するという心境の変化です。世間でも「三日会わざれば刮(かつ)目(もく)して見よ」と言われるそうです。「努力をしている人は三日もすれば大きく成長しているので、次に会うときは注意してみなければならない。」とのことです。私は努力していません。しかし、法蔵菩薩さまが私の中でご修行してくださっていることは信じられ
るのです。こちらからの自力の生活では考えられません。不連続です。ところが如より来生せる廻向のおはたらきは一貫して連続しています。一筋に生長させられるのです。生活、人間性に現れてくるのです。
全く変わらない面は私の縁に触れて起こる悲しく、愚かな煩悩です。浅ましい身の迷いの真実です。ここはどうなっているのか。
親鸞さまは、後世の求道者がこういうところで壁にぶち当たり、行き詰まると見越しておられたのでしょうか。信の巻の中に次のようにお書きになっておられます。
誠に知りぬ。悲しきかな、愚禿鸞、愛欲の広海に沈没し、名利の太山(た
いせん)に迷惑して、定聚(じょうじゅ)の数(かず)に入ることを喜ばず、
真証の証に近づくことを快(たのし)まざることを、恥ずべし、傷むべし、
と。
聖典二五一
『教行信証』は親鸞さまが浄土真宗の教えを公(おおやけ)にして、後世に残しておくために心血を注がれたご書物です。その中に、このようなご自身の痛切な告白を書いておられるのは私利私欲や名誉を捨てておられるからでありましょう。そして後の私たちが本当に救われるために、すべてをさらけだされて間違いなく「あなたはあなたのままで、本当に救われるのですよ」と呼びかけてくださったからこそ、今でも機が熟した時、親鸞さまの教えが生きて聞こえてくるのではないでしょうか。ここまで正直に書き残された人は日本でも、世界の聖人(せいじん)でもあまり見られないことです。
私などはここまで書いていただかないと、自分で自分をごまかしたり、あきらめて前へ進んでゆけません。彼の願力に帰依させられ、歩み続けることは不可能です。大石先生、藤解先生や数々の先生方、そして名も知れぬ同行様方が本当に親鸞さまに従ってゆかれたお陰で私も親鸞さまに従い導かれてゆかされます。
1月23日付けの毎日新聞の社説に、経済中心の価値から、社会とのつながりや生活の満足感や幸福度を重視する社会の転換を呼びかける文章が掲載されました。真宗の信仰の盛んな地域に幸福度が高いことは前から知られています。必然に、報恩の感情も強いのです。梅干と思っただけで口の中につばがにじむように、報恩講と思うだけで、温かく、楽しく、わくわくするという報恩講が長く続いてきました。ところが、戦後社会情勢が変わり、あらゆる面が重なって報恩講も前の熱気が薄らいでいます。しかし、心の世界はいくら世の中が変わろうと人間あらん限りご縁次第で氷の心が水のように変ったり、熱い湯の心に変わらされます。
このたび、お華束(けそく)盛(もり)や花立、幕(まく)張(はり)、掃除、仏具みがきなど当番地域の皆様と作業しながら温泉の湯につかったような楽しいひと時を過ごさせて頂きました。こういう時代だからこそ、何かお互いに大切なものに帰りたいという心がはたらいているように感じられました。こういうご縁の場があってよかったな。と静かな喜びが沸いてきました。親鸞様、如来さまからのご功徳であります。
25日午前3時ころ、お知らせがありました。「永遠に自分の思いが無くなるのは恐い淋しい、ではなかった。我執から出る思いは迷いであり本来何もなかった。あるのはご本願。本願から生まれ、本願に生かされ、本願に帰らされる。」思わずメモに書きとめました。私が6才の時、祖母のスガばあちゃんが亡くなりました。それから何日間か木を見ても、「この木が大きくなったら僕はこの世にいない」。赤ちゃんを見ても「この赤ちゃんが年を取ったら僕はこの世にいない」と思うと淋しく、悲しくなりました。五(ご)右(え)衛門(もん)風呂(ぶろ)で「こう思っている思いがずっとなくなってしまう」と思った途端に大声を出して泣いたのを不思議に憶えています。62年たって深く眠っていた問いがようやく解(と)けました。
「ご本願(光)から生まれ、ご本願(光)に生かされ、ご本願(光)に帰らされる」。なんと有難いことか。親鸞さまのみ教えのお陰であります。
令和6年1月末日
常照 拝


- 帰命となってからは、仏様と私の関係が変わるのです。私に対立して仏様
を考えるのではありません。対立が摂取に変わるのです。仏様は生きてお
られるからこそ衆生を救済してくださるのです。仏様は絶対の智慧(光
明)です。絶対の智慧ですから、対立している私を包んでくださいます。
絶対の智慧から慈悲が現れて、対立に閉じこもっている私に、親のみ心を
知らせたいと願われるのです。その慈悲が具体的に活動に現れるのを方便
と申されます。この智慧と慈悲と方便とが、混(こん)然(ぜん)と溶け合っ
て活動してくださっているのがご名号なのです。
書信64信―9
このご文章を幾度拝読させて頂いたか知れません。しかし、読めていなかったのです。だから二回や三回読んでわかる世界ではありません。「江本の文章は門徒さんにはわからん」同級生のお言葉です。一面そうだろうなと私も思わされます。「小学校4年生でもわかる表現をすること」と言われて、それも否定できません。かみ砕いて、かみ砕いてお伝えするのもこれからの私の仕事であります。
先日、法友の方からのお便りで気にかかるお言葉がありました。
私は正しい。その思いから人を裁いている事に気づかされ、昨夜は眠れずに
苦しかった。常にその心で人と接しているのかな。助けて下さい。お念仏で
す。
すぐに返信を書かされました。
環境のせいもあって、私は小さい頃から内向的、自虐的性格でずいぶん悩み苦しみ、したがって暗かったのです。夜は不眠症でした。天上の木目の模様がいろいろ奇妙に見えたり、鳥の声におびえました。青年になると人間関係が嫌いになり一人で山や川に行きました。
大石先生にご本願の世界そして滅度の世界をお教え、お育ていただいて、お念仏一つで何もかも消して下さるように成らされました。
今はあの大きな苦があったればこそ。と、如来さまの大慈悲のご恩を深く感じさせられています。
親鸞さまは
「無始以来の苦においては、二三の水滴のごとし。滅すべきところの苦は大海の水のごとし」。
と龍樹(りゅうじゅ)菩薩(ぼさつ)の教えを引用されています。慶びが海のごとしではなく、二,三滴(てき)の苦しみはあっても、のぞかれた苦しみは海のごとし。という表現に実感がこもっています。
さて、毎日戦争と政治の腐敗のニュースが流れ気持ちが落ち込んでしまう人もありましょう。 ニュースキャスターも大谷選手の話題の後(あと)「こういう話題だと心が晴れます」と思わず漏(も)らされたのも同感するところであります。
釈尊は「苦」という問いを問題にされました。
先日、ベラルーシのスラーバさんからリモート法座の時、ご質問がありました。「四諦(したい)を浄土真宗では説いているのですか」私は「説いています」とお答えしました。四諦とは、苦諦(この世は苦しみに満ちているという真実)、集諦(じったい)(苦しみの原因は煩悩にあるという真実)、滅諦(めったい)(苦しみが滅(めっ)するという真実)、道諦(どうたい)(苦しみを滅するために正しい方法があるという真実)です。
私は滅度ということを大石先生から聞かせていただいたとき不思議な気がしました。藤谷秀道先生が「教行信証の証巻はこれからだ。これまで行巻、信巻までで一杯だった」と仰せられていたことが心に残っていたからです。確かにそれまで滅度というお教えはほとんど聞かなかったことでした。しかし、親鸞さまは証巻の初めに
正定聚(しょうじょうじゅ)に住(じゅう)するがゆえに、必ず滅度(めつど)に至る
と言い切られておられます。
蓮如上人は信心獲得(ぎゃくとく)章(しょう)のお文の中で
されば無始以来つくりとつくる悪業煩悩を、残るところもなく、願力不思議
をもって消滅するいわれあるがゆえに、正定聚不退のくらいに住(じゅう)す
となり。
滅度は肉体が死んでからの世界ではありません。我執が滅せられた世界であります。そしてそこが帰る世界となり、はじまりの世界です。法蔵菩薩さま誕生の世界です。私は夜寝るとき、しばらくお念仏しています。いつの間にか寝ています。朝、目が覚めると昨日のことが頭をよぎります。お念仏のないときはいつまでも過ぎたことにとらわれ、引きずっていました。「ああ、この迷いにとらわれ、自分で自分にだまされていたんだ」とお念仏と共に立ち上がり、前進さ
されます。生活の中、仕事の中でもそういう連続です。だから、忙しい中を精一杯全力投球させて頂けます。寝ても覚めてもいのちのある限りは称名念仏さされます。
大石先生の「光あり」の歌の中には「法蔵菩薩は光といのち」というお言葉があります。
親鸞さまの「正信偈」の初めには
無量寿に帰命いたします
不可思議光に南無いたします
光のいのち(仏様の慈悲)と人間の思議を超えた光(仏様の智慧)のはじまりです。光の命の誕生でありますから、帰命された人は明るくなるはずです。では、法蔵菩薩さまはどのようなおはたらきをなされているのか。
親鸞さまが十八願のみ心を信の巻に詳しく説いて下さっています。くどいようですがしばらく辛抱して読んでください。如来さまのみ心、十八願(至心(ししん)、信楽(しんぎょう)心(しん)、欲生(よくしょう)心(しん))をおおざっぱに意訳(いやく)させて頂きます。時間が無くて丁寧でなく申し訳ありません。
至心(ししん)、私どもが無始より今日、今の時に至るまで、穢(え)悪(あく)汚染(わせん)にして清浄の心はない。嘘(うそ)偽(いつわ)りばかりで真実の心が無い。だからこそ、如来さまが法蔵菩薩となって私どもの身、口、意の業の中に下(くだ)り入(はい)って、無始よりこのかた今日、今に至るまでどんな瞬間でも休むことなく清浄で真実の心でご修行をして下さり、さわりのない、説くこともできない功徳を私達凡夫ににどうでもこうでもして与えようしておられる。そのお心を具体的にかたちにあらわしたのが至徳の尊号である。
信楽(しんぎょう)心(しん)、私どもが無始より無明の海に流転し、無明を無明とも知らずに同じ過(あやま)ちを犯(おか)しては迷い、沈み、苦しみから抜け出せない、あわてて偽りの善や行をして光明土へ至ろうとする。しかし、それでは決して生まれることはできない。だからこそ、如来さまの大慈悲心から法蔵菩薩と下がられて私の身、口、意の三業の中で浄土に生れる因を与え、さわりのない広大の浄信を与えられた。「大経」には諸々の衆生が如来さまがお名号と成って下されたお心が届いて信心歓喜が起こった。
他力の信心はすこやかで楽しい世界です。かたぐるしいのは自力が入っているからではないでしょうか。「正信偈」には
煩悩の林に遊びて神通を現じ、生死の園(その)に入りて応化(おうけ)を示
す、といえり。
とあります。大変な境地ですが、遠くにしていてはいつまでたっても堂々巡りで一生が過ぎてしまいます。
欲生(よくしょう)心(しん)、私どもが煩悩の海に流転し、生死の海に漂い沈んで、真実に浄土へ向かう廻向の心が無い。清浄に浄土へ向かう心が無い。だからこそ、苦悩の私どもを救わんとして、無始より今日の今まで法蔵菩薩が私どもの身、口,意の三業の中で如来の大慈悲心を届けるために働きづめである。この欲生心が届いた文を「大経」には、至心に廻向したまえり、かの国に生れんと願ずれば、すなわち往生を得(う)、不退転に住せんと。ただ五逆と誹謗(ひぼう)正法(しょうぼう)とを除く、と。
ここで、注意されることがあります。帰依したら五逆はなくなる、誹謗正法は消えてしまうと軽く受けとってしまいます。ところがいよいよ深く自身の法を盗む在り方、法に逆らう姿が照らされます。それが如来さまのご廻向と知らされますといよいよ有難く、ご恩報謝のお礼の念仏が出て下さるのです。ここのところを大石先生にお育て頂きました。そのご恩は言葉にできません。先生に如来さまにご身労をおかけした関所であります。
昔の同行さん方は如来さまを親様と呼ばれました。救われてみれば親様に多大なご苦労をおかしたとそのご恩を感じずにはおられなかったのでしょう。現代でもこの事実は生きています。
さて、もう一つ苦について、釈尊の教えとして、四門出遊(しもんしゅつゆう)という教えがあります。苦しみをかかえていたゴータマシッダールタ太子(仏になる前の釈尊の呼び名)は、苦しみから抜け出すために城壁から外に出ました。最初に東の門から出て老人を見ます。「あなたも老いますよ」と言われて失意にくれます。次に南門から出ると病人を見ました。「あなたもいつかは病気になります」次に西の門から出ると葬儀の列に会いました。「あなたも必ず死にますよ」と言われて失意のどん底に落とされます。そして、最後に北の門から出て沙門(しゃもん)の老いて崇高(すうこう)なお姿を見て「あのようになりたい」という願いを起こされて出家を決意した。と言われています。沙門(しゃもん)とは出家者の事です。その沙門はよほど崇高なお姿とご尊顔をされておられたに違いありません。
「大無量寿経」には、釈尊がお覚りを開かれてご説法されるお姿に感動された阿難尊者が
諸根(しょこん)悦(えつ)予(よ)し姿色清浄にして光顔巍巍とまします。
とあり、さらになぜそのようになったのかを説くために、自分が発心したとせずに、釈尊のお心に現れた法蔵比丘が世自在王仏さまを讃(たた)え、願いを起こされるという他力回向の深い思し召しが説かれています。
光(こう)顔(げん)巍巍(ぎぎ)として、威(い)神(じん)きわまりましまさ
ず。〜〜
如来の容顔(ようげん)、世に超えてともがらなし。
私は人間である大石先生のお姿、ご尊顔の上にこの事実と通ずる世界が近づけば近づくほど感じさせられました。そして、ご本願が信じられるように成らされたのです。日々、年々このご恩の慶びが深められていることであります。そのご恩は親や先祖、家族、周りの方々と広がる事であります。
二十八日の朝、散歩に出かけました。太陽が遅く昇(のぼ)るためでしょう。しばらく月と日の出を楽しみました。景色の色がだんだんと色づいて開けて来ます。贅沢(ぜいたく)な時間でした。
年の瀬に 月と朝日を楽しめり
常照
この度もこの通信をもって年賀状とさせて頂きます。令和六年もお育ての事、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和五年十二月二十九日
常照 拝


- 尽(じん)十方(じっぽう)の無碍光(むげこう)は
無明の闇をてらしつつ
一念歓喜する人を
必ず滅度にいたらしむ
曇鸞和讃
この頃、朝夕の勤行中に浄土から響いてくるご和讃に出遇わされます。滅度という世界は私においては遠くの世界でした。藤谷秀道先生から
「親鸞さまの『教行信証』の証の巻はこれからだ」
とお聞かせいただいてから四十五年の歳月がたちます。
大石先生からは信後の生活のあり様として、証の巻さらに『浄土論註』のお教えをかみ砕(くだ)いてお育てをいただきました。親鸞さまは証巻の初めに必至滅度の願(十一願)・難思議往生(十八願)をかかげられています。日常生活では聞くことのない難しい言葉が続いて申し訳ありません。しかし、私においては根本的に大事なことなので少し辛抱(しんぼう)してください。
私は仏教の書物を読んで理解していったのですが、だんだんと暗くなっていきました。仕事も行き詰まり、家庭生活もギクシャクしていきました。勉強した仏教の教えは生活の中で生きて来(こ)なかったのです。ですから、なお落ち込みました。思いの仏教に絶望し、思いの自分に絶望していったのです。言葉だけがぐるぐる回って牢獄に居るようでした。
そういう中であったから、大石先生に出遇えたのでしょう。先生のどこに魅(ひ)かれたのか。そのことが現れているご文章に最近遇いました。
念仏は仏の御智慧と申しておられます。果(は)てしない智慧ですから、光明
無量とか尽十方無碍光とか表現してくださいます。言葉で現わしたらもう絶対
ではなくなります。だが言葉に出さねば救済のてがかりがありません。そこで
「いろもない、形もない、心も及ばず、言葉も絶えた法性法身」から口に称え
易い御名号となって現れて下さったのですから、お念仏が出て下さった時に
は、形無き世界に往生させて頂いているのです。だから言葉が消えるのです。
言葉や理論で証明する必要がないのです。証明しようとしたり、認めさせよう
とする我が消えるのです。又証明し認めさせる相手も消えます。だから信ずる
とか、信じられぬとか、疑いが消えます。唯(ただ)、ほれぼれと、仏様の広大
なる光明の天地と一つにとけ合っていることを、仏願のおかげ、師教のおかげ
と、感謝させて頂けるのです。その感恩の心も仏様からたまわったものですか
ら、「南無阿弥陀仏」とみ名を称えて報謝さされるのです。
書信63
形の無い世界、言葉や知識や感性では及ばない世界です。ところが深い悲しみや苦悩がご縁となって苦しみや悲しみが超えて行けるという事実があります。私がその通りでした。
お釈迦様はおさとりになられてしばらくご説法をなされませんでした。娑婆世界の主たる梵天(ぼんてん)が尊いおさとりの境地を説いて下さいと釈尊に請(こ)い願いました。しかし、お釈迦様はなかなか説かれませんでした。なぜなのか。いろもない、形もない、言葉も絶えた世界です。世間の価値で生きているのが大多数の人です。出世間の法を説いても、ほとんどの人が無関心か、さっぱりわからないか、反発するしかないことがわかっていたからでありましょう。それでも、梵天は「あなたのお教えに遇ってひとしれず深い悲しみ、苦悩にあえぐ人が救われます。どうか、説いて下さい」と。何度も懇願(こんがん)されたのです。
仏伝(ふつでん)には「私が説いたならばかえって人びとに害をするのではないかと思ったからである」と書かれています。もし説かなかったら今日の仏教はありませんし、今ここの私達はありません。
ふと思わされます。「さっぱりわからない、反逆する、無視してわすれてしまう」は誰のことか。実は私自身であったのです。今もそうなのです。その中で一刻も休みたまわず私の内外で法蔵菩薩様(如来様)がはたらき続けて来たのでした。今、書かされているこの瞬間もです。たとえば心臓が寝ていようが、腹立てていようが、なまけていようが働き続けておられるように。もし休んだら生きていけなかったのです。
藤解照海先生が「念仏を離れたら生きていけない自分に遇いなさい」とおおせられたのはこのことでした。私は肉体の藤解先生にはお遇いしたことはありませんが、大石先生の中に、CDテープや日めくりカレンダーで毎日のようにお育てを頂いています。藤解先生の背後に親鸞さまがいつも生きておられます。親鸞様のお心が、ご本願が生きて伝わってきます。単なるお勉強や学問、知識ではないのです。生きて響いてきます。生活がそうなっておられるからでありましょう。私において念仏の道を本気で歩ませて頂こうと決心させて下さったのは先生方のお陰であります。
大石先生が私の真宗聖典の証の巻を開かれ、次のご文を人差し指でなぞられました。
それ真宗の教行信証を案ずれば、如来大悲廻向の利益なり。かるがゆえに、
もしは因もしは果、一事として阿弥陀如来の清浄願心の廻向成就したまえる
ところにあらざることあることなし。因浄なるがゆえに、果また浄なり。知
るべしとなり。
二つに還相の廻向と言うは、すなわち利他(りた)教化地(きょうけじ)の益な
り。〜〜『浄土論註』に顕(あらわ)れたり〜『浄土論註』をひらくべし。
この事は、私の人生を方向づけられるほどの象徴的出来事でした。
滅度、浄土、涅槃とは人間心の一点の交わらない清浄、真実の世界であります。身心ともに濁りきった、悪業煩悩の人間とは真反対の世界です。だから絶対に救われるはずのない人間が救いにあずかれるのです。ただただ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と仏恩報謝のお礼のほかありません。
親鸞様は十八願のお心を三心にわけて教えてくださっています。なぜなのか、くどいほど人間は無始以来清浄の心が無く、真実の心がなく、沈み救いようのない煩悩具足の凡夫であると念を押されています。「だからこそ、お前自身に遇ってくれ、本願真実に救われる、本願を信じ、たのめ」と確信をもって教えてくださっています。
アメリカ、ニューヨークを発つ前日はゲーリーさん宅でのご法座でした。ゲーリーさんご夫妻はドイツ系アメリカ人です。毎日の勤行は日本語読みの『正信偈』とご和讃です。来年の三月に教師の資格を受けられるため日本に来られるそうです。第一番のご法話を長仁寺でされることになりました。
ご法座はお文様一帖(ちょう)四通(つう)のご縁でした。
問うていわく、「正定聚(しょうじょうじゅ)と滅度とは、一(いち)益(や
く)とこころうべきか、また二(に)益(やく)とこころうべきや。」
答えていわく、「一念発起のかたは正定聚なり。これは穢土(えど)(娑
婆・世間)の益なり。つぎに、滅度は浄土にてうべき益にてあるなりとこ
ころうべきなり。されば、二益なりとおもうべきものなり。」
浄土にてうべき益を、肉体が死んだ後と解釈したら真宗の救いは台無しです。お釈迦様の無我の教え、涅槃の境涯は絵にかいた餅のようになり、生活とおおよそかけ離れたものになってしまいます。十八願の念仏往生、他力の信心を頂くということは、浄土を頂く事、浄土に生れる事です。二十年ほど前でしょうか、熱心な坊守さんが長仁寺へ来て本当に求めて聞いている人がいると驚かれました。その反応に私が驚きました。その坊守さんにとっては、本当の救いは死んだ後で、この世ではそういうことを聞いておくぐらいな位置づけなのだろうかと不思議に思いました。
人のことではない私自身がそこの大事なところを曖昧(あいまい)にしてきたことを知らされました。アメリカでの忘れられないお土産と成りました。
さて九月十三、十四日は富山県南砺市の浄円寺(重共聡住職)の本願道場にて嬉しい出遇いがありました。信心の香りが残っている土地がらの中、八十五才の藤井貢さんが五箇山から車で一時間以上かけて二日間ご参詣下さいました。藤井さんはあの有名な同行である赤尾の道宗さんの血が流れているとお聞きしました。道理で何かたのもしい念仏者の風格を感じたはずでした。
藤井さんは二十代のころ藤解先生を訪ねて広島へ四,五回行かれたとのこと、人生に迷い、苦しくて何度か直接に電話をされたそうです。藤解先生からの答えはいつも「ただ心静かに念仏申しなさい」だったとのこと、不思議に私にも深く伝わってきました。藤井さんにとって六十年間その願いが生き続けています。その日、新潟県から来られていた、林康一朗住職さんが「私はその一言が最大のお土産に成りました」と言って喜んで帰られました。懇親会も世間話はなく、楽しい仏法談義でした。蓮如上人が長い旅路を来られた同行さんに冬は酒を燗にし、夏は冷やしてねぎらわれたのはこういうことなのかと思わされました。にぎやかな懇談の中で私は中島けい子さんという坊守さんに「ほんとうを求めて、ほんとうに成って下さい」と申し上げました。そんなことを言う私でないから、如来さまに言わされたのでしょう。言った私が驚きました。中島さんは一度長仁寺へ行きたいと妙敬寺の坊守さんに言われたそうです。
また、その場の雰囲気を見ていた「みんなの金曜日」という店のおかみさんは「次の時は私もその中にいれて下さい」という要望があったことを重共さんが伝えてくれました。おかみさんは障害者のお子さんがおられ、グループでお弁当を作る店もしておられるそうです。
二十日、三重県松林寺(森愚英住職)の本願道場では愛知県から杉山さんが初めてつれてこられた布施(ふせ)さんという女性が終始泣いておられました。なぜ泣かれるのか聞かれませんでしたが、その後、杉山さんから布施さんも含めて五人で新潟の等覚寺・圓性寺報恩講にご参詣する連絡を頂きました。最近、何か少しずつご本願の火が燃え広がって来つつあるのを感じさせられます。
最後に二人の同行さんを紹介します。
前略、渡米前のお忙しい折にかかわらず、ありがたい大石先生の冊子「念
仏の親子」「生きていてよかった」「リモート法座(一)」通信第七十六号
長仁寺報第三十三号をお送りくださり、何度も読み返しております。お礼が
遅くなり恐縮しております。
今後とも聞法を続けさせていただけるご縁をまことにありがたく、深く感
謝しております。
わからないまま、どうあっても聞法を願うわたくしのこころには、法蔵菩
薩さまのおはたらきが届いている不思議を味わっております。
「後生の一大事」という言葉を聞かせていただきました。これからもどう
か、よろしくお願いいたします。
草々
なむあみだぶつ 合掌
三橋祥江 拝
千葉県にお住いの三橋さんはアメリカにおられる名倉さんのリモートを通してのご縁です。法蔵菩薩さまのおはたらきが味わえるまで聞法を続けてこられたお方ですから宿善の深い方だと思われます。いちど長仁寺にも参詣したいとのことです。これからの歩みが楽しみです。
次に、九月二十六日から二十八日にかけて新潟県からご参詣の明岸寺住職法隆光昭さんのお便りです。
謹啓 秋分の頃 皆様、ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。
先日は、二泊もお世話になりました。御法座の時間だけでなく、一日中
ずっと、聞かせて頂きました。ありがとうございました。
法座が終わると仏法のことは忘れます。常照先生は「だから勤行が大事な
んや」と。私は勤行を軽く考えているなあと思います。
今回、なるべく私のフィルターを通さず聞かせて頂きたいと思っていま
した。そうして一歩引いて見ると、言葉や表現を聞かせたいわけでなく、
本願に触れさせたいんだなあと感じさせられました。
「生活の中で、如来様如来様と。如来様がどこにいるか探せ」という趣旨
のことを、kさんにお話しでした。私も、その通りだなあと聞かせて頂き
ました。
何か知って得になったというのとは違う、ただ楽しい時間でありまし
た。ありがとうございました。取り急ぎお礼まで。
季節の変わり目ゆえ、どうぞ体調を崩されませんようご自愛くださいま
せ。
合掌
かなめのところを受けて下さって有難いです。すたれていく寺院が多いなかで光明土へ向って明るくなっていかれる皆さんに触れて本願力が湧いてくると申しますか、元気が出てきます。共に浄土の中で浄土へ浄土への歩みであります。
令和六年(2024)十月四日
常照 拝


- 新緑がまぶしい程に輝いています。四月はゆっくりできる時間が与えられて、畑に行くことが出来ました。ジャガイモの芽かきをして知らされました。実を結ぶためには土、肥料、植え付け、草取り、芽かけ、土かけ、等々たくさんの手間がかかる。人間が実りある人生を送らせていただくためにはもっともっとかかる。ましてや、信心の行者が誕生し、育つために親様(如来)、よき師のお手間をどれくらいかけたか知れない。・・・・南無阿弥陀仏。
仕事が楽しくできる。生きているそのままが楽しい。十八願の三心(至心(ししん)・信楽(しんぎょう)心(しん)・欲生(よくしょう)心(しん))に信楽(しんぎょう)心(しん)(如来のよろこび願う心)とあります。私には生きているのがただ苦しいという長い期間がありました。「人はあんなに楽しそうにしているのになぜ自分にはないのだろうか」とよく思いました。苦しい思いの下には信楽(しんぎょう)心(しん)が発起するための準備期間が必要であったのです。また何をしてもむなしくなぜか気力が出ないという長い期間がありました。それは欲生(よくしょう)心(しん)(如来の純粋意欲心)という芽が出るための準備期間であったのです。そして、自分も他人にも汚れた心や嘘が見えていやになる。真実はどこにあるのかわからない、しかし、どうにもならない。というあの期間にも至心(ししん)(如来の真実心)が動いていたのでした。如来の三心(一心)は人間世界になかったのです。聖徳太子が「世間虚仮、唯仏是真」、親鸞さまは「煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろずのこと、みなもって、そらごとたわごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておわします」とお教え下さっていたのです。ジャガイモ様をご縁として如来さまからのご廻向のお教えでした。
また、こんなに大地の功徳を有難く感じさせられたことは初めてです。心身が癒され、鳥の声に和(なご)まされ、風呂、食欲、睡眠が十分に与えられるもったいない御利益であります。浄土論(願生偈)に地功徳の教えがあります。身を通して味わわされます。
このたび五年以上使わせていただいた長靴に穴があき、いよいよはけなくなりました。穴の開いた長靴を本堂の前に行き阿弥陀様の方に両手でささげてお礼を申し上げました。そういう心にいつの間にか成らされていることが有難いことでありました。その時、「この身心もお与えくださり、十分に使って頂いて役が終わる時は本当にお礼だな」としみじみ思わせて頂いたことでした。
私は八月に七十才、古希(こき)を迎えます。あと十年すれば八十才です。早いですね。私は本願のみ教えがなければ、心身が弱まり焦(あせ)りが出て、なさけなくなるだろうと思います。ところがご本願のお陰で年と共に本願の味わいが深く強くなっています。
藤谷秀道先生は親鸞さまのご一生を九歳で芽が出て(出家)、二十九才で法然聖人と出遇われ、つぼみとなり、五十才を過ぎて「教行信証」の完成で花が咲き、八十三才を過ぎて円熟された。と先生が八十五才ころの法話テープの中で語っておられます。身を通してのお教えですから味わい深く響いて来ます。
曾我量(そがりょう)深(じん)先生が藤代(ふじしろ)聡(とし)麿(まろ)先生に「長生きをしなさい、仏法が深く味わえる」との仰せが今の私に響いて来ます。身体の弱体化はどうする事も出来ませんが「正信偈」の中に
惑(わく)染(ぜん)の凡夫、信心発すれば、生死(しょうじ)即涅槃なりと証知せしむ
との親鸞さまのお教えがあります。そのお味わいを「生、老、病、死のままに救いあり」と大石先生からお聞きしました。
仏法の教えでなければ、こういう世界は味わえないことでありましょう。世間では老いはさけ、病を嫌い、死を忌(い)み嫌い恐れるだけであります。ところが生まれた以上絶対に逃げられない事実であります。私の人生においてもこれまでご縁に遇った多くの方々がすでにこの世にはいなくなりました。そういうことをこの頃ふと感ずるようになりました。老、病、死が身近になって来たからでありましょう。
大石先生は「クラス会と言っても年々人数が減り、やがて幻(まぼろし)の会と成る」とお書きになっています。人情で言えば淋しいことです。そこで考えてはだんだんと力が衰え、弱まっていくという事実を受け入れざるを得ないこととなるのでありましょう。逆らえば苦しむばかりであります。
現代の日本人は平等と言う理念のもとに、競争をして社会の批判や主張をし、何かを勝ち取ることで成果があがったという価値感にかたよりすぎた勉強をして、正しい受け身の教育が弱くなってきた気がします。経済中心のあり方について疑問を持つゆとりがありません。宿業・本願という尊い教えは教育の中にありません。
不平不満が多い日本人の在り方を物語っている新聞記事を前号で書かせて頂きました。幸福度が先進7か国の中で最下位、世界でも147か国中55位ということでした。一見意外でしたけれども必然のことでもあるのです。未来がないと若い人たちの声があります。「その頃わしらは死んどる」とはお年寄りの捨て台詞(ぜりふ)です。考えてもしようがない。元気なうちに好きなことをして、おいしいものを食べ、旅にいこうというような本がベストセラーになっています。テレビは食事、旅の番組それから過去のドラマでいっぱいです。「こんなことで人間に生まれた甲斐があるのかな」と思わせられます。
四月からのNHKの朝ドラに「何のために生れて、何をして生きるのか。わからないなんて、そんなのはいやだ」という言葉がよく出て来る「あんぱん」というドラマがはじまりました。私はあまり見ていませんが本屋さんでもやなせたかし先生の本がたくさん並んでいます。多くの人の心の底にいつも問われているテーマでありましょう。解決のつかないままで、時は容赦(ようしゃ)なく過ぎていく、ふと我に返ると浦島太郎のように白髪の老人になっている。という人が少なくないのではないでしょうか。
ところが暗くなるほど星や月が輝いてくるように、不可思議な功徳の道があるのです。生老病死を出る道が仏道であります。若きお釈迦様の苦悩を深めたのは老、病、死の問題でした。そして、ついに解決の道を求めて出家されたのでした。
私どもには幸いに聞法の道があります。人として円熟していける道であります。先月の輪読会の後、嬉しいお便りが届きました。
若葉の季節となりました。いつも輪読会ではお世話になります。我執の強い私は、聞いても、聞いても仏様の声がいまだ届きません。が、聞かせて頂く事で少しづつではありますが、私の在り方は、何かちがう、おかしいと気づかせてもらえる瞬間に出遇える時、ああ、聞かせて頂いてよかったと思う現状です。年と共に根気が失われつつありますが、これからも御教導の程宜しくお願いします。
大山京子さんは耶馬渓のお寺の坊守さんです。心が若々しい方です。必ずご質問を七,八回は
されます。質問される方は深まりが早いです。ご法座の後のよろこびの表情に私の方がいつも
救われます。
宇佐市の渡辺和義さんからもメールが届きました。渡辺さんは十年以上前から三か月に一度自宅で本願道場のご法座を開いて下さっています。
本日の輪読会は、ことのほか有難い僧伽(さんが)(法の集い)でした。無明と光は三界(さんがい)(欲界、色界、無色界)の外(そと)にあり、機の深信と法の深信に対応している。
煩悩は無明から生じるので自分の意思でコントロールできるものではない。無明の闇を破(は)するのは、本願念仏しかない。向こうから私に御廻向される光(本願念仏)が届くとき、我が身に法蔵菩薩が誕生する。それを聞法精進により感得するのです。
こういうふうに受け止めさせて頂きました。みなさんご熱心で時のたつのも忘れてしまいました。長仁寺の僧伽はありがたいです。
南無阿弥陀仏
私よりも如来さまが慶ばれる感じがいたしました。人にお伝えできるまでなられるよう念願いたします。
通信に対してのご感想のお便りも届きました。高木さんは大石先生宅の御法座でいつも昼の弁当のお世話をしておられた方です。
続いてお世話様になります
先ほどポストに通信の封筒を見つけ、早速読ませて頂きました。有難うございます。
もう一度と思って読ませて頂きますと、今読ませていただいたのに、はじめての様なのです。私のために有難うございます。
私も毎朝、大石先生のご書信を読ませて頂いていますが、百回以上繰り返し読ませていただい
ているのに不思議に毎日初事のように新鮮です。この世でそのようなよき師、ご文章のご縁を頂
いていることに無上の幸福感を味わわせて頂いています。
以前、新潟の林康一朗住職さんのご案内で曾我量深・平澤(ひらざわ)興(こう)記念館にゆき、教えて頂いたこと
があります。平澤先生の色紙の裏に書かれていました。
「学問(聞法)は、はるかに先をゆく人を追いかけるような態度ですべきである。追えども追えどもおいつけず、油断すると見失ってしまうような気持で勉強すべきだ」( )は筆者。
私にとっての大石先生が、その通りの師であると言いたいところです。少し近づけたと思う瞬
間に、はるか先を歩いておられる。これが実感です。
二十七日の聞光道には千葉県から三橋(みつはし)祥(よし)江(え)さんがご参詣くださいました。欧州法座も見学したいとのことで二十六日から二泊されました。二晩とも夜中の十二時ころまで白熱の座談でした。追体験と言うことがありますが大石先生を囲んでの法座はいつも白熱がありました。ご書信に書かれています。
教えを受ける方も、人情や、学問、道徳や人間の努力ではついてゆけません。限界があります。挫折します。師と弟子との双方の奥に本願力が働き、ちょうど刀鍛冶が刀身を熱して、鋼(はがね)をつけるようなものです。双方が白熱してくると、刀匠の一(ひと)撃(う)ちで鋼がぴたっとつきます。最近は道を求める法友と、よく語り合います。願わくは、こう有りたいと思います。
書信73信―7
また、思い出すことがありました。私が苦しくてどうしようもないとき、「江本さんが地獄に落ちているならわたしも落ちて私が先に救われる」と書信に書かれています。大石先生は上から引き上げるのでなく、むしろ姿勢の高い私の下に降りられて、先生が苦しい時代のことをよく語られました。私と同化され、お育て下さっていたのです。しかし、私は苦しいばかりでもがきが続きました。
同じ子供でも病気の方の子が親にはいつも気にかかるように、私の中の如来さまは病の重い子が気になるようです。私の中の如来さまの活動がそのようにお働き下さることを通して、私は先生に手厚くお育て頂いてきたのかと思わせられるのです。
一昨年の十月に法喜さんと道人君が長野県の善光寺さんへ行った時の土産話(みやげばなし)です。「戒壇(かいだん)めぐり」という綱(つな)をたどってしか進めない、真っ暗な回廊があった」ということを思い出しました。私たちは意識無意識を問わず無明(真っ暗な流転の闇)の人生を教え(綱)をよりどころに進んでいけるのでしょう。教えがなければ、「そらごとたわごと」の中で一生が空しく過ぎたということになります。一人ひとりに突きつけられた問題であります。
つくづく、よき師、よき朋(とも)、尊きみ教えのご恩を知らされることであります。皆様、そして如来様に南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と頭(こうべ)を垂(た)れるほかあません。その心も私には無く、如来さまからのご廻向のたまわりものであります。
令和七年(2025)五月五日
常照 拝
お知らせ
五月十二日(月)十一時より四時ごろまで東本願寺・同朋会館の一室にて
京都本願道場が開かれます。ご参加の方は十日までにご連絡ください。


- 五月二十三日、友松法(ほう)純(じゅん)さんのお見舞いに行きました。十年ほど前から心臓の大手術を二回されています。現在は透析(とうせき)をされて体重は四十キロ前後です。息子さんの徹(てっ)心(しん)さんから「生死のことは如来様におまかせしたと父から言われました」と、お聞きしてから二年近くたちます。コロナもあり面会時間は十分です。三カ月前の見舞いの時、万歳の姿でお別れしました。その時のお慈悲の眼が胸に焼き付きました。
以前、よく言われていました。「長男を事故で亡くし、心臓病をかかえている自分が家内より先に行くとばかり思っていたのにがんのために家内が先に行くとは夢にも思っていなかった。あの時、長仁寺さんで大石先生にお遇いしなければ私はとっくに死んでいた」と。あれから二十年たちもうすぐ八十八才です。「よくここまで生きて来られた。大石先生、如来様、皆様のお陰です。朝目が覚めたら、ああ、今日も生きていたと思わされます。有難いです」と。今回の眼はずいぶんくぼんでいます。大石先生が最後の瞬間まで完全燃焼されたお姿と重なります。もうすべてからからに炭が燃え尽きた先生のお姿でした。
法喜さんが「境内の植木鉢のバラは時間がたつと弱くなり枯れていくのに、地に下ろしたバラはあんなに大きくなって見事な花をつけている。人間のはからいの枠の中では弱り、細ってしまう。大地に根を下ろすとたくましくなる。法純さんは本願の大地から力をいただいている」と、その通りだと私も知らされたことでした。
このたびのお見舞いで印象に残ったのは「ただ、南無阿弥陀仏。我も仏もない、ただ南無阿弥陀仏、お礼です。この世界をお伝えください。たのみます」と手を広げて合掌されました。何か深く余韻が残り病院を後にしました。そして深く響いて来ました。
念仏する我が残ったり、仏を信じる我が残ると法に執着します。法を利用して自我を押し立てるのです。法執の大問題です。ここは人間心では超えられません。そこを超えられなければ、宗教我、宗派我、国家我、民族我は超えられません。二十願の念仏の不定聚のありかたと十八願の念仏の正定聚のありかたと異なるところです。十九願、二十願の世界は十八願の世界を包めません、わからないのです。しかし、十八願は二十願を包めます。そこを通ったからです。大石先生は「仏法は仏法のためにある。仏法は仏法でしか受け取れない」と仰せられたことがあります。
法蔵菩薩さまの誕生が一大事であります。すなわち第十八願、他力回向の信心が発起する時であります。人間をご縁として起こる信心でありますが、人間が起こす自力の信心ではありません。永遠界を有限界が受け止められるはずはありません。有限界は無限界に摂取されているのです。
蓮如上人のおおせにも
「心得たと思うは、心得ぬなり。心得ぬと思うは、こころえたるなり。弥陀の
御たすけあるべきことの尊さよと思うが、心得たるなり。少しも、心得たる
と思うことは、あるまじきことなり」と、仰(おお)せられ候。
蓮如上人御一代記213か条
我も仏もないとなった無我の世界こそ、あらゆる民族、宗教、国と違いのままに手を取り合い、励まし合い、協力していけます。この世界が人類を地球を救う根拠となりうるでありましょう。
この願いに燃えて次の日の第四十三回、欧州法座に臨みました。日本の通訳の山口英道さんは曹洞宗の禅の僧侶です。海外ではベラルーシ、オランダから、ブルガリアから、ウクライナ出身者、ロシアの方そして日本の方。宗教や国、民族を超えています。中国仏教の研究者であるイリーナさんは最初の頃たくさんの専門的質問をされました。しかし、次元の異なる世界を感じられたのでしょうか。最近はじっと聞いておられます。今回も「興味深いお話でした」との感想を漏らされました。マキシムさんは禅から入られた方です。「お念仏するとつつまれる感じがします」との実践的な感想でした。通訳のオレグさんは、「日本では、なぜたくさんの如来をまつっているのですか」というご質問に「如来は形の無い真如ですから業に応じて化身されるのです」また、「どうして真宗はブッダから始まらずに、弥陀の本願から始まるのですか」というご質問には、「釈尊(ブッダ)が目覚めようが、目覚めまいがダルマ(法)は法、本願は本願です。ブッダが法(本願)を発明したのではありません。法に目覚めた第一人者なのです。ゴータマ(ブッタ)の時期には家族があり、子どももおられたのです」。「ありがとうございます」。
私は四十年くらい前から解けなかった「隻手(せきしゅ)の音声(おんじょう)」という禅の公案が最近解けたので山口さんに聞いていただきました。両手でたたけば音が出ます。片手の音を聞けということです。私は「それは聞こえないということではないですか」「そうです、ただしあとの半分があります」「ほう」しばらくして「南無阿弥陀仏」。「さすがですね。その通りです」法純さんからの一連の背景があったから如来さまが現(あら)われたのでしょう。最近、皆さんの表情が穏やかで明るく成られました。一か月に一度三年以上続けられていることは本願の力でありましょう。弥陀の誓願不思議に皆さんと共に助けられています。「スパシーバ(ありがとうございます)、南無阿弥陀仏」となごりおしいお別れの挨拶のもと、来月を楽しみに今回のご縁が終わりました。
後日ご書信でまた展開されて響いてきました。
断四流(だんしる)(生老病死)の断というのは、往相廻向の他力の信心を
頂けば、その信の一念に、願力の不思議をもって、四生(胎、卵、湿、化)
のなか、受くべき生もなく、六趣(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上)
のなか、おもむくべき趣(くに)もないようにして下さる。・・・悪果を招く
業因をことごとく滅ぼし、その結果も受けないようにして下さるのである。
ゆえに、一念に速やかに三界(欲界、色界、無色界)の生死を二度と受けな
いように断ち切ってしまうのである。これを断というのである。
歎異抄の第一章では、聖人の話し言葉として、「念仏申さんと思いたつ心の
おこる時、すなわち摂取不捨の利益にあずけしめたまうなり」と申しておら
れます。
書信56-12
長い間、何の疑いもなく相対界の計らいで良し悪し、損得、勝ち負けしかないと思い続けて来た、その無明の闇が晴れる時です。法、本願をよりどころとする生き方がはじまる時が念仏の時です。
この頃、各地の本願道場が燃えて来た感があります。岐阜の森はる美さんが言われます。「ユーチューブやリモート法座もいいけど、やはり生(なま)の法座は違う」と、確かにプライバシー保護の問題もあって白熱したところがカットされます。後半の座談が白熱します。そこは生(なま)で参加するしかないでしょう。
富山の重共聡(浄円寺住職)さんも「御法座の空気感が違いますね。皆さん真剣です。ですから、自信をもって求道の人に呼びかけられます。あの空気の中におれるだけでも有難いです」という電話でのお話でした。
私は十八願の世界に焦点を絞っているからだと思わされました。もちろん初心者がおられればその方に応じて法話が出て下さいます。でも力が沸いてくるのは十八願とその後の歩みです。そのように私は大石先生、藤谷先生、藤解先生にお育て頂きました。今でもです。そこに焦点があたるとぐんと参加者は減ります。でも貫かされます。十八願には立てないと平気で言う説教師が昔から多くいます。現代ではそれも聞かなくなりました。ご法座が減り、参詣者も激減しています。三日間勤めていた法要が一日となり、一座となったと嘆きの声を何度も耳にします。実は今に始まったことでもなく、親鸞さまの当時からもあったのです。
濁世(じょくせ)の群萌(ぐんもう)、穢悪の含識(煩悩・悪業に染まったも
の)、いまし九十五種(外道)の邪道を出(い)でて半満・権実(小乗仏教・
大乗仏教)の法門に入(い)るといえども、真なるものは甚(はなは)だもって
難(かた)く、実(じつ)なるものは甚だもって希(まれ)なり。偽なるものは甚
だもって多く、虚(こ)なるものは甚だもって滋(しげ)し。
旧聖典 326頁
像末五濁(ぞうまつごじょく)(形だけの像法、仏法が末になっている乱れ
た世の中)の世となりて
釈迦の遺(ゆい)教(きょう)かくれしむ
弥陀の悲願ひろまりて
念仏往生さかりなり
正像末和讃 旧聖典502頁
五濁悪世の有情の
選択本願信ずれば
不可称不可説不可思議の
功徳は行者の身にみてり
正像末和讃 旧聖典503頁
五濁とは辞典によると、
世の末に顕れる五種の社会的・生理的・精神的な汚れ、乱れ、衰え。一、劫濁(こうじょく)とは世の末に諸悪が増すこと。二、衆生濁とは世の初め純真であった衆生が世の末になると十悪をほしいままにすること。三、見濁とは自己の悪をすべて善とし、他人の正しさをみな誤りとすること。四、煩悩濁とは悪性のため見るもの聞くものすべてに貪瞋をおこすこと。五、命濁とは見濁・煩悩濁のため多くの生命をうばい、他をいつくしみ育てず、その結果自己も長生きできず短命となること。〜〜五濁の世には弥陀の本願を信ずるよりほかに救われる道がないとする。
とあります。五濁悪事悪世界は毎日の新聞や報道番組をみればあきらかなことです。しかし、弥陀の本願を信ずるという報道はありません。テレビニュースからは愁嘆の声ばかりが聞こえて来ます。
二億年前の恐竜時代は一〇〇〇年に一種類の生物が滅び。二、三百年前は四年間で一種類。一〇〇年前では一年間に一種類。一九七五年には一年間に一〇〇〇種類。現在は一年間に四万種類の生物が滅びていると知らされると。870万種類の生物がいつまで地球上に残れるか。人間の悪性、罪の深さは計りしれません。
さて、五月は京都の東本願寺(同朋会館)で第一回の本願道場が開かれました。そのいきさつは、最近あまりに忙しいので十二日のリモート法座はしばらくお休みすることとなりました。ふと、京都の円徳寺前住職の佐藤淳さんには通信は送らせて頂いているけれどしばらく音沙汰がありません。佐藤さんは私が本山におるころ、役宅に遊びに来てくれた人です。法要にも何度も法話に行かせて頂きました。電話をしたところ、パーキンソン病が進んで車、単車の運転も出来なくなったとのこと。近くにある同朋会館まではいけるということです。ならば、かねがね本願道場が京都で開かれればと願っていたので同朋会館に連絡したところ一室を借りられることになりました。九州から私と法喜さん、河野久美子さん、岐阜から森はる美さん、愛知県から水上幸枝さん、土田タズコさん、富山から立野奈津子さん、湯浅久子さん、中島けい子さん、そして京都の佐藤さんの十名の同行さんが集われました。すぐに打ち解けて内容の濃い白熱した座談会となりました。六月は渡辺和義さん末子さんご夫妻と大山京子さんも加わり九州から六名参加予定となりました。本願が熱を発して活動が現れて来た感じがいたします。大石先生について、北海道や富山、山口、ブラジル等に行かせていただいたことが思いだされます。
中国の曇鸞さまがお書きになった『浄土論註(じょうどろんちゅう)』の最後の最後に
ロバにまたがっていくことが出来ないような愚かな者でも、転輪聖王の行列
に従っていきさえすれば、たちまち虚空にかけのぼり、あらゆる世界に思いの
ままに遊行して、少しも障害となることがない、というようなのを他力と名づ
けるのである。
愚かではあるが、浄土の法(みのり)を学ばんと後に続く者よ、他力に身をま
かせるべきむねをよく聞いて、信心を起こすべきである。決して自分だけの小
さな思いにひっこんでひとりよがりにならないように。
で終わっています。
この文章の直前に次のような文章があります。
たとえば人あって、三塗(地獄・餓鬼・畜生)の苦しみを恐れるために、い
ろいろな禁(かい)戒(りつ)をまもることによって禅定を修し、禅定によって神
通力を身につけ、神通力によってありとあらゆる世界に遊行できるようにな
る、というようなのを自力と名づけるのである。
解読浄土論註 下巻170頁
はじめて読んだ時、感心して読んでいたらひっくり返されて、「え、なぜ」と思わされたことをよく覚えています。今ふりかえると、自力心で燃えている、熱があると思っていた時は、思いであって本願は燃えていなかったのです。
森ひなと言うお同行さんの有名なお言葉に「他力、他力と思うていたが、思う心がみな自力」まさにそれが私の姿でした。自力で空回りして、人数や世間の価値基準に振り回されていたのです。
活動が始まるから、明るく、温かくなり、周りが見えてきます。自身の無知、無力、無能にたじろがず、本願力に乗せられて前進であります。そのみ力でこの通信も書かされているのです。師恩、仏恩であります。
令和七年五月二十七日
常照 拝


-
私自身、どう生きていいのか分からない長い年月を経て、「永遠の光」
に遇い得たのです。
慈悲の光は人間の力では受け取れないのです。人間の考えで受け取った
ら、人間の考えがそこに残ります。光に遇えば、受け取ろうとする我が消
えて「ありがとうございます」となるのです。そうなって初めて「一切こ
の世界のことは、阿弥陀仏の身口意の三業の世界であるということが分か
ってくる」のです。
「我(が)」でもって、一切如来様がやっておられると、思えるものではあ
りません。「仏法は無我にて候(そうろう)」は、光明に摂取された後にう
なずけるのです。
でも、一度(ひとたび)その世界に出ても、この世にあって生活をしてい
る限り、仕事一つをとっても、考えが異なると、衝突は起こります。
それでは駄目なのか。さにあらず。帰命の一念の後は、仏様に使って頂
くということが根底になるから、善きも悪しきも仏様に帰らせて頂くので
す。
帰らせて頂くたびに、だんだんと仏様の徳が身に満ちて下さるのです。
親が子のために 苦労するほど、親心が深くなってくるというものでし
ょうか。帰命となっても光明に摂取されませんと、私にはそこのところが
味わえませんでした。そうなりますと、我(が)というものは幻影であり、
非実在であり、本当の我(われ)というもの、言葉をかえて言うと本当の実
在というものは、この天地を一つに見る阿弥陀様の光明の中の一徳々々と
して存在していることが分かるのです。その時、お念仏が口に出て下さる
のです
大石先生ご書信58―11
長い大石先生のご文章ですが私においては長年のもやもやしていたことが聞こえて来た慶びがあります。
「一切この世のことは、阿弥陀仏の身(しん)口(く)意(い)の三業の世界であるということが分かって来る」。裏を返せば私は、我(が)から身・口・意の三業によって罪をつくり、欲界・色界・無色界(人間の思想・主義・意見)の三界をへめぐり、むなしい生活をして来たことが照らしだされて来たのです。
「人生、何のために生れ、何をして生きるのか。本当の生き甲斐(がい)は何なのか」。この問題を解決した人がいた、迷いを迷いと、闇を闇と目覚めさせてくださる世界があった。無碍光(むげこう)とか不可思議光といわれる帰るべきお浄土(光明海)への道が開かれていた。その道を歩いて下さった大石先生そして親鸞様。さかのぼれば釈尊はじめ七高僧、蓮如様、無数の先生方、先輩方のたどられた救いの道が確かにあった。さらに私も煩悩具足のままに従(したが)っていける。有難(ありがた)い光の世界との出遇いでした。
先生との出遇いから浄土の世界に触れ、お育てを受け、「弥陀タノム」が発起されてから、私は腹底から「何のために生れて、何のため生きるのか、何が生き甲斐(がい)か」が決着されたのです。「生まれた甲斐があった」と腹底から言えます。「ありがとございます。私の宿業の人生をいただきます」が出て下さったのです。そこから、私の宿業の生活の中で仏法を味わわせて頂ける人生が始まったのです。
次に、浄土論(願生偈)の最初にあります
世(せ)尊(そん)我(が)一心(いっしん) 世尊、我一心に
帰命尽(きみょうじん)十方(じっぽう) 尽十方無碍光如来に
無碍光(むげこう)如来(にょらい) 帰命して
願生(がんしょう)安楽(あんらっ)国(こく) 安楽国に生れんと願ず
我一心の「我」「一心」は人間の我なのか、人間の一心なのか。
池山(いけやま)栄吉(えいきち)先生の有名な句に
われ(我)ならぬ清らのわれ(我)のわれ(我)にありて
穢(え)悪(あく)のわれ(我)をわれ(我)にしらしむ
穢悪の我(が)の中に人間心の汚れの入らない我(われ)、すなわち法蔵菩薩の願生心が誕生された。そこを出発点として浄土をよりどころとした人生が始まるという事でしょうか。
それまで物質的にしか見ていなかった世界が少しずつ変わって来ました。一つ一つの形は「宿業・本願」という内容として味わわされてきます。大石先生は「阿弥陀様の光明の中の一徳々々として存在していることが分かります」との仰せです。曽我先生は「宿業(しゅくごう)共感(きょうかん)の大(だい)地(ち)」とか「感応道交(かんのうどうこう)」というお言葉を残されています。長い間、私はそれらのお言葉を味わうことが出来ませんでした。
「一心」。よく大石先生は「海に入ったら川の名前が消える」と仰せられました。娑婆の差別・相対界を川にたとえられ、川から見た良し悪し、損得、好き嫌い、大きいとか小さい、遅いとか早いという日ごろの心のありさまを教えて下さいました。そこには常に劣等感や優越感が根底に流れています。心の底からの満足感はどのようになっても得られません。それで私はいつも深い満足感が無く、何か得体のしれない不安がつきまとっていたのです。
今、同じ不安が起こってもお念仏一つで浄土へ帰れます。だから、生きていることが有難くなりました。楽しくなりました。「天上(てんじょう)天下(てんげ)唯我独尊(ゆいがどくそん)」は絶対界、永遠界、すなわちお浄土から見られた世界です。光明の海から川を見たてまつる世界があったのです。川の名前が消されて、劣等感、優越感から解放された広々とした光明界に入ると「ただ、ありがとうございます。なむあみだぶつ」とご恩報謝のお念仏が出て下さるのは必然のことであります。
名号不思議の海水は
逆謗(ぎゃくほう)の屍骸(しがい)もとどまらず
衆悪の万(ばん)川帰(せんき)しぬれば
功徳のうしおに一味(いちみ)なり
尽(じん)十方(じっぽう)無碍光(むげこう)の
大悲大願の海水に
煩悩の衆流帰しぬれば
智慧のうしおに一味なり
曇鸞(どんらん)和尚和讃
永遠の光の誕生について、釈尊までさかのぼりますと、仏伝の中に釈尊の成道(じょうどう)(おさとり)の夜のことがくわしく述べられています。その日の夕暮れに「縁起」によってさとりを得られた。とあります。
釈尊は内観によって、なぜ苦しいのかを問われました。
① 「老い、死」がある。②「生まれたからである」、何によって「出生」があるのか、③有(う)(迷いの 生をくり返し、輪廻的生存がる)、④取(しゅ)(執着がある)、⑤愛(渇きのごとき欲望がある)、⑥受(じゅ)(感受がある)、⑦蝕(しょく)(接触がある)、⑧六処(しょ)(眼・耳・鼻・舌・身・意の六つの感覚器官)、⑨名色(みょうしき)(名称と現象)、⑩識(しき)(識別する働き)、⑪行(ぎょう)(迷妄な生活の内容をなす諸行為)、そして一番根本に⑫無明(おろかさがある)。この根本無明のおろかさから苦しみの人間生活が成されていた。無明(おろかさ)に目覚めた時。
起こるのである、起こるのである。実に、比丘たちよ、以前には聞いたことのない 無明を自覚せしめた法(ダンマ)に私の眼が開け、理解が生まれ、了解が生まれ、智慧が生まれ、光が生まれた。
仏教聖典40頁
苦しみの根本無明(おろかさ)に目覚(めざめ)させた、永遠の光(法)との出遇いが説かれています。
愚(ぐ)禿(とく)親鸞(しんらん)の「愚(おろか)」であります。大石先生の初めの文章では「我と言うものは幻影であり、非実在であり」とあります。光に遇って無明(おろかさ)の我(が)が消されたのであります。
私においては「無明(おろかさ)の我(が)から一切を見ていたのが、大間違いであった。我(が)からの念仏や信心を利用して我(が)を通そうとしていた。大馬鹿者、大罪人でありました。ただ、申し訳ありませんでした。よく知らせて下さいました」と懺悔と報謝の世界が出た時であります。それが私に「弥陀タノム」が起こった時でした。七年前のその時は地味でピント来ませんでしたが、月日と共に報謝と懴悔の心が自分でも驚くほどに生長さされて来ました。
次に、釈尊伝の夜中の偈では、法の目覚めによって、無明からの迷いの連鎖が消滅し、新しい世界が展開されたことが書かれています。
以前には聞いたことのない法に対してわたしの眼が開け、理解が生まれ、了解が生まれ、 智慧がうまれ、光が生まれた。
と、繰り返しおおせられています。
浄土真宗の教えから頂くと、法は本願であり、光明のおはたらきであります。本願念仏は光であります。十八願のお念仏が口に出て下さるとは、人生に光が生じることであります。無明の闇(やみ)の心に太陽が昇る事であります。生・老・病・死のままに明るくなるのです。
その世界を大石先生は「本当の実在というものは、この天地を一つにみる阿弥陀様の光明の中の一徳々々として存在していることが分かるのです。その時、お念仏が口に出て下さるのです」とのおおせです。
さらに、夜中の偈には、
天眼をもって死につつある者、生まれつつある者を見た。業に従って貴賤となり、美しいも の、醜いもの、良い境涯、悪い境涯へ行くのをわたしは知った。
とあります。ここは注意が必要です。インドのヒンズー教は輪廻転生の教えがあります。この世では報われないが次の世では高い位につくと解釈すればカースト制度すなわち一、バラモン(宗教者)、二、クシャトリヤ(武士、貴族)三、ブァイシャ(庶民)四、シュードラ(被支配者、先先住民)の階級制度を守るための教えになってしまいます。釈尊はカーストを超えて僧伽(サンガ・法を聞く集まり)を開かれました。そこでは、身分によらず先に入った人が先輩となるあり方です。しかし、現在のインドでは仏教はヒンズー教の一派としての位置づけとなっています。インドは仏教国ではなくなりました。
日本でも宿業と宿作外道の区別がつかず自分の境遇を運命としてあきらめるという意味で宿業を解釈すれば、江戸時代の身分制度(士・農・工・商・穢多非人)を維持するための教えとなります。そうなれば目覚めの教えが本分(ほんぶん)をわすれて堕落してしまうこととなります。
宿業なしに本願の救いはありませんし、本願なしに宿業の救いはありません。法なしに業はなく、業なしに法はありません。法をよりどころとして法に生きる。本願に生きる教えが仏教です。
釈尊の内観は明け方になるとさらに展開します
心が静まって〜〜煩悩の消滅を知る智慧に向けた。これは苦である(苦諦)と、これは苦の生ずる原因である(集諦(じったい))と、これは苦の消滅である(滅諦)と、これは苦の消滅に到る道である(道諦)と、ありのままに知った。
仏教聖典47頁
四聖諦(ししょうたい)(苦・集・滅・道)と言われる教えです。
そのように知り、そのように見たわたしの心は愛欲の煩悩から解脱し、生存の煩悩から解脱し、無明(おろかさ)の煩悩から解脱した。解脱した時「もう生れ出ることは無くなった。浄(きよ)らかな道は完成した。なすべきことはなし終えた。さらにこのような生を受けることは無い」と知った。〜無知は消えて智が生じ、闇は消えて光が生じた。
それは安逸に流れずに熱心に努力している者の上にまさにそのように生ずるのである。
仏教聖典48頁
成道直後のできごと
〜〜〜もろもろの法が明らかになるとき、彼は魔軍(まぐん)を粉砕(ふんさい)している。あたかも太陽が大空 を照らすように。
ところが、解脱のよろこびを味わっている中で釈尊に次のような念(おもい)が生じた。とあります。
この法は、世間一般の在り方に逆らい、微妙(びみょう)で甚(じん)深(じん)、見難(みがた)くかつ精細であるから、欲を貪(むさぼ)り暗黒におおわれている人々には、とうてい見ることができない。
世尊の心は説法することに傾かず、無関心だった。
ここに、娑婆世界の主たる梵天(ぼんてん)が膝を大地につけて世尊に向って合掌し、こういった。
「願わくは法を説きたまえ。世間には、塵(ちり)にくもらされることの少ない人びともおります。けれども、彼らとても法を聞かなかったならば、滅び衰退してしまうに相違ありません。この世間には法を了解する人々もありましょう」。
世尊はこの梵天の懇願(こんがん)をしり、かつはまた、世の人びとに対する慈(いつく)しみにより、仏(ぶつ)眼(げん)をもってこの世間を熟視(じゅくし)したもうた。〜〜〜
「耳ある人に甘露(かんろ)の法門が開かれたのだ。耳ある人びとは聞け、己(おのれ)れの信を離れよ。
梵天よ、わたしが微妙なすぐれたる法を説かなかったのは、もし説いたならばかえって人に害をするのではないかと思ったからである」。
仏教聖典58頁
「己の信を離れよ」とは娑婆の常識(道徳や損得、良し悪し、世間体の信(こころ))を置いてさとりの世界を聞いてほしい。ということです。これはなかなか難しいことでありまさす。世間でよくできている人ほど難しいことでもありましょう。
釈尊から三千五百年たって便利になったけれども人類のありさまの本質は同じであります。
悲しきかな、釈尊の死後、少しずつ、尊い教えが、人間の考えで解釈され、形式化していきます。
おおよそ五百年を経過して、龍樹菩薩、また四、五百年して天親菩薩などによって大乗仏教が起こり本来へ帰ろうと呼びかけて下さったのです。そのお流れを親鸞さまが「正信偈」に詳しくお説きくださっています。また恩徳讃の直前の御和讃に他力の信心を得る人をお釈迦さまが親友といわれてよろこばれる。と申されています。
他力の信心うるひとを
うやまいおおきによろこべば
すなわちわが親友(しんぬ)ぞと
教主世尊はほめたもう
聖典505頁
親鸞様からさらに七五〇年を経た今日、最近の日本では朝夕の勤行は少なくなり、仏壇(ぶつだん)じまい、寺じまいさえ珍しくなくなりました。そして、最近の人々は老いも若きも国や人類の将来に希望がもてず、未来に明るさを感じないという声を耳にすることが多くなりました。根本の無明・光明の問題はお説教の場でもあまり取り上げられません。そのために宗教や教育や政治や経済に明るさや力強さがなくなり、何が本当の依り処なのかわからないという風潮があります。
いくら便利になっても、お金があっても、将来に希望が持てず、意欲が無くなれば、生きてゆく力が湧いてきません。空(むな)しくなり、投げやりになり、犯罪にも手を染めやすくなります。世界中が暗闇の中で、またもや軍備拡張という方向に流されています。未来がない、光がないということでありましょう。蓮如上人の「あわれとうも、なかなか愚かなり」(白骨の御文)の通りのありさまです。
しかし、どのような時代になろうと、「南無阿弥陀仏の一声で、釈尊と等しいさとりの境地、功徳大宝海が煩悩具足の凡夫に頂かれる」。というのが親鸞さまのみ教えであります。それは人類救済の根本となれます。しかし、深く真剣な聞法がないと信じられることではありません。仏伝では「安逸(あんいつ)に流れずに熱心に努力している者の上にまさにそのように生ずるのである」とあります。私には「聞法を怠らないように真剣に聞いてくれよ」と叫んでいるように聞こえて来ます。
さて、五月二十九日から三十一日、新潟県の圓性寺・等覚寺本願道場。六月五日、宇佐市・渡辺本願道場。十四日から十七日の京都、岐阜、三重本願道場には法喜さんと大山京子さん河野久美子さんが同行されました。河野さんが「江本さんご夫婦が大石先生に遇いに行っているような後ろ姿でした」と、聞光道で感想を述べられたのがうれしかったです。それぞれの方がさまざまな宿業をかかえながら熱心に聞法されています。各地で熱気のある座談がもたれました。圓性寺住職の林さんが忙しい中、法話のテープ起こしをして下さりました。それぞれの方が本願のみ力に乗せられて歩まされています。私は苦しみから解放されたご恩に突き動かされています。
娑婆(しゃば)永劫(ようこう)の苦をすてて
浄土無為を期(ご)すること
本師(ほんじ)釈迦のちからなり
長時(じょうじ)に慈恩を報ずべし
救いの道が、今、ここに開かれてあり、案内して下さるよき師がおられる。よき朋(とも)がおられる。私の生き甲斐はこの道をたどらせて頂くことです。光明の中を、光明土へ、お浄土へと。
そこには、大石先生の微笑みが常にあります。
令和七年七月初旬 常照 拝


- 二十二年間ご縁を頂いた我が家の猫(ジャス子)が早朝、二時十分ころ息を引き取りました。老衰です。二十二年間のご縁でした。人間でしたら百十六才ということです。ジャス子は訪ねて来られる多くの人に挨拶に出てきました。皆さん印象に残るのでしょう「ジャス子はどうしていますか」という声をたくさんいただきました。
ご法座の終わり、「光あり」の歌のとき、なぜか察知して「私に対して歌うのよ」と言わんばかりに皆さんの前に現れました。法要の終わりにも門徒さんが「ジャス子」と呼びかける声が珍しくありませんでした。
この二日間、家族でそれぞれが何度となく、「南無阿弥陀仏、ありがとう」をくりかえしました。そういわずにおれないお徳がジャス子の方にありました。
今朝、畑に野菜の水をやり、草を取っている時、「そのままの救い、十八願」という声なき声が聞こえて来ました。大石先生が「生・老・病・死のままに救いあり」また「ああそうですか」と言う世界。禅宗では「あるがまま」・「眼(げん)横(おう)鼻(び)直(ちょく)」、藤解先生は「どうにもならんちゅうこっちゃ」私が金沢駅で聞こえた「どうしましょう。どうする必要もなかろう、わしがおろう」と次々にお言葉が沸いてきました。
ジャス子は死に逆(さか)らうことなく、あるがままの姿を見せてくれました。
弥陀如来は如(にょ)より来生(らいしょう)して、報(ほう)(阿弥陀仏)・応(おう)(相手の根機に応じて現れる仏身)・化(け)(かりに形を現した仏身)種種の身を示し現わしたまうなり
教行信証・証巻
私達を救いに猫の姿をした如来様のご化身であったのでありましょう。ジャス子の死を前にして私は気にかかるある方に電話ができました。また、孫の結縁(ゆいえん)君が死にゆくジャス子の前で、最近の心配事を涙ながらに語ってくれました。死の報告のために音信が途絶えていた二人のかたとやり取りが出来ました。ジャス子は死んでまで救いのはたらきをしてくれました。
さて、最近、普賢菩薩の事が気にかかってきました。お聖教の中によく登場されるからです。辞書によると普賢とは「仏の至極の慈悲、仏の大慈大悲の徳。また浄土に往生した者の還相回向の徳」とあります。
親鸞様が七十八才の時にお書きになられた「唯信鈔文意」の中で
このさとりをうれば、すなわち大慈大悲きわまりて、生死海にかえりいりて、普賢の徳に帰せしむともうすなり。
聖典549頁
私は大石先生や藤解先生のご縁が無ければこのようなご文章は読み過ごしていたに違いありません。そうなっておられる得道の仏者にご縁を頂いたことは無上のご恩であります。
また、「歎異抄」の第四章、「浄土の慈悲というは、念仏して、いそぎ仏になりて、大慈大悲心をもって、おもうがごとく衆生を利益するをいうべきなり」。第五章の「ただ自力をすてて、いそぎ浄土のさとりをひらきなば、六道四生のあいだ、いずれの業苦にしずめりとも、神通方便をもって、まず有縁を度すべきなり」などはどこか自分とは縁遠いこと、肉体が死んだ後の事のようにしてしか読めなかったでしょう。
子供の事、寺の事など心配が重なって、うつ状態になったことが私にはあります。妄念妄想が沸く中でお念仏が出て下さると一瞬妄念妄想が消されました。でもまだ帰命とはなっていませんから一瞬は消えても、また自分の思いや世間体(せけんてい)の方に帰り苦悩は続きました。
今も妄念、妄想は絶え間なく起こってきます。しかし、帰る世界が違うのです。清沢満之先生の「他力の救済」のみ教えが生きて聞こえてきます。
我、他力の救済を念ずるときは、我が処するところに光明照らし、我、他力の救済を忘るるる時は、我が処するところに黒暗覆(こくあんおお)う。〜〜〜
もし世に他力救済の教えなかりせば、我は終(つい)に迷(めい)乱(らん)と悶絶(もんぜつ)とを免(まぬが)れしなるべし。
蓮如上人の信心獲得章のお心も、身の事実として響いて来ます。
南無と帰命する一念のところに、発願(ほつがん)回向(えこう)のこころあるべし、これすなわち弥陀如来の、凡
夫に廻向しましますこころなり。これを『大経』には「令(りょう)諸衆生(しょしゅじょう)功徳(くどく)成就(じょうじゅ)」ととけり。されば無始以来つくりとつくる悪業煩悩を、のこるところもなく、願力不思議をもって消滅するいわれあるがゆえに、正定聚不退(しょうじょうじゅふたい)のくらいに住すとなり。
聞法を続けると認知症になりにくいと同行さん方に、私はよく申し上げてきましたが、もしお
念仏の教がなかったら、私自身が認知症やうつ病になりやすいタイプの人間だと知らされます。
そういう私がお念仏に救われる時、人の幸せを願う心が発起し、ただちに活動が始まるのです。すべてお師匠様のお陰、有縁無縁の皆様そして背後にずっとお見捨てなく働き続けて下さった如来さまのお陰であります。お念仏に救われた功徳として「何のために人間として生まれたか」「何をして生きるのか」がはっきりさせられて来ました。
普賢菩薩にもどります。「浄土論註」の終わり近くに本願力によって、自利(じり)利他(りた)の救いが成就することを三つの願を根拠にして説いておられます。十八願の念仏往生の救い。十一願、必至滅(ひっしめつ)度(ど)の救い。第二十二願に救われてからの活動。
「弥陀の本願をたのむ」となるまでは私は自分の思い、努力心をたのんでいたのです。それなりの世間の成果もありました。だが、続かなかったり、失敗と思われることが数々ありました。
ところが、帰命となってからは大きく世界が変わってきました。九ケ所の本願道場が開かれ、月三回のリモート法座、ユーチューブ江本常照、フェイスブック。さらに、海外の同行さんとのご縁が広がってきました。ユーチューブ江本常照の視聴者は八十人くらいです。ご法座も参加者は十人くらいです。それが少ないのか、多いのか。疑問に思っていましたが、無数ということを知らされました。数字の何千、何万はその人だけのことです。法座のお一人の参加者の背後には無数の先祖や先輩方がおられたのです。
また、岐阜の森はる美さん宅は十二月までに古家(ふるや)を改築されて聞法道場を建立されることになりました。今月は駐車場を広くするために木の移動などをされていました。ご主人さんは森住建の社長さんです。「なぜこういうことをするのか自分でもわからないところがある」と漏(も)らされました。みなご本願力に動かされているのでしょう。本願寺も木造建築では世界最大級の大きな建築物です。そうせずにおれない本願のみ力があるのでしょう。
私は森はる美さんに数年前から頼まれていた法語カレンダーを完成記念にしようと思い立ちました。取り掛かると不思議と三日間で原本が出来上がりました。第一日目は「一生懸命にやってできなかった事が、本願力によって実現できている」です。
道場の再出発のご縁で道場名を、「池田町、志願・無願本願道場」とさせて頂きました。ご主人の法名、志願は「大無量寿経」の志願倦(う)む(なまける・くたびれる)ことなし。はる美さんの法名、無願は聖典の同じページにある空、無相、無願の中から頂きました。ずいぶん交通の不便な所と思っていましたが、ご本願が発起(ほっき)されたら、実現されることを見せて頂いています。第一回目は私達を入れて十一人の参加者でした。これからが楽しみです。
高岡の浄円寺本願道場も回を重ねるごとに、一人、二人と真剣な姿勢の参加者が増えてきました。十八日のご法座は休みなしで三時間、十九日も休みなしで二時間。皆さんの真剣な眼に時間のたつのも忘れてしまいました。映画でも三時間は通しで見られません。「不思議だな」と、私も皆さんも思わされたことです。今回本堂から演台に出て行く時、蓮如上人にご挨拶するとはじめてお軸の讃(さん)が目に留(と)まりました。
慧(え)燈(とう)大師(だいし) (蓮如上人は闇夜の中に在って、智慧の灯(ともしび)をかかげ)
以大荘厳 具足衆行 (大荘厳をして、法蔵菩薩・普賢菩薩の願行が衆生・蓮如上人にはたらき)
令諸衆生 功徳成就 (もろもろの衆生に 浄土の功徳が成就されてゆく)()は筆者意訳
私は如来さまに操(あやつ)られるごとくご説法させて頂きました。重共(じげとも)聡(あきら)住職さんが最後のご挨拶で「本堂の阿弥陀様が慶んでおられます」と締めくくってくださいました。
さて、今月は高岡へ行く途中、新大阪駅で下車しました。四十四年前に東大谷のお墓でご縁があった和田安弘さんとの夕食を共にすることになっていたからです。京都で一別以来七年ぶりです。和田さんは私と同年で耳鼻咽喉科のお医者の先生です。学生時代に金子(かねこ)大榮(だいえい)先生のご長男さまに数学を習い、息子さんにも数学を教えて頂いたそうです。受験に通るための勉強ではないとの条件だったとのことです。大榮先生にも直接お宅でお会いすることがあったそうです。食事中に言われます。
「在家の人間に、正しく、心おだやかに生きていける教えを説いてほしい。そして、わかりやすい表現でお願いします」と何度も言われました。また、自身の事を「自分のストライクゾーンが広がった」と言われました。それは和田さんの人格が大きくなられたと私には感じさせられました。
数日してメールが届きました。
本日の心に残る金言集
南無阿弥陀仏
しゃあないなあ〜
またの機会を楽しみにしております
「弥陀たのむ一念」を読んでいて、乗り過ごして今、西院で降りました。また戻らねばなりません。これが本当のしゃあないなあ〜です。
一昨日お会いして、江本さんはこれから仏法を通して、在家の伝道者となられ輝かれるような気が致しました。
コロナ前に京都でお会いした頃に比べても、より好きな雰囲気になられておられました。二人で会えば大谷墓地事務所の頃に簡単にワープ(瞬間移動)できます。こちらに来られましたら、気楽にお声がけ下さい。
和田医院の玄関を入ると仕事を終(お)えた看護師さんたちが掃除をされていました。機敏な体の動き、それぞれの方のご挨拶がとても印象良く、院長先生が喜んで待っておられることを皆さんもどこかで喜んでおられるような気がしました。開院して以来辞められる看護師さんが少ないとのことです。
大石先生の「道には道の、木には木の、妻には妻の、夫には夫の、仕事には仕事の使命がある。それぞれの使命を輝かせる使命がご本願です」とのお教えが生きておられるように感じさせられました。
浄土の救いの生活を歩ませられるとはとてつもない事のような気がします。しかし、また凡夫(ぼんぶ)の在家者にそのことが実現しなかったら経(きょう)教(きょう)は絵にかいた餅(もち)でしかありません。あわてて急ぐことはできませんが、毎日生活の中でためされ、味わわされます。大石先生が「誰も歩いていない真っ白い雪道を一人で歩いてゆくようなもの」と言われました。私は先生の足跡をたどっている感がありますが、私の宿業の中では誰も変わってもらえない二河白道の道であります。
最後に機縁熟して先生のみ教えが響いてきたご文章をいただきます。
今、私は仏様を念ずる時、刹那にお浄土に生れ、刹那に娑婆に帰ってくるーそんな気持ちです。「そんな馬鹿な」と、人は思うかもしれません。私もかつては想像できなかったことですから、無理に信じなさいとは申しません。信じられることではないからです。だが、仏様の方からの本願力のお働きが届いたら、信じられようと、信じられまいと、仏様の方が広大な世界を恵んでくださいますよ、ということは、心で申し上げたいのです。
書信・第59信の16
このような表現になるまで消化されるのは日常の生活の在り方、生き方がご本願に一貫されているからでありましょう。また、先生が「本願が信じられたら生活に一本、筋が通る」と散歩中に申されたことが思い出されます。どんな大木も一つのいのちです。幹も枝も葉も違っているようで一つのいのちが流れています。「願いに生きる」「人の幸せを願う」私にはあり得ないことです。しかし、大石先生によって、私の宿業の台木(だいき)に本願の木が接ぎ木され、思わぬ展開がくり広げられて来ました。南無不可思議光の世界であります。
令和七(2025)年八月初旬 常照 南無

真宗大谷派 普光山 長仁寺
本願道場
〒871-0104 大分県中津市三光諌山1161-1
電話0979-43-5017