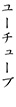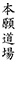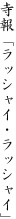『通信』「長仁寺報」 一覧 ≫ 大石法夫先生御書信
大石法夫先生御書信

- 今日は十二月三十日です。今から丁度十二年前の今月今日、新館に御師匠様がでてこられて御話しされました。
「この一年間いろいろと苦労なこともあったが、それを超えてこられたのは佛様のおかげであったと、それを喜ばせて貰いましょうで。これが大事なのですよ。」
「どんな苦難が来てもそれを受けてゆき、突っぱなしてゆける力を貰うたからこそ有難いのです。これが名号不思議の力というものです。」
「どうにもなるものではないということが、わしの八十五年間の結論ぢゃ。指のないおじいさんを二年七か月世話したが、わしが貰った菩提心を引き出す役目をしてくれた佛様でありました。」
「人生に苦労はつきもの、楽をしようと思うのがまちがいです。」
当時私は御法話を速記したり、御話しの後覚えていること、心に残っておることをすぐ書きとめておりまして、そのノートが三分冊になっております。この御法話は五十一年の今日の日づけになっており、ノートにかいてある文をそのままここに載せました。括弧は私がつけて、お話を四つの部分に分けて書いたのです。
第三信に教行信証の総序文の冒頭の御文を原文のまま載せまして、難解な語句には註釈をつけました。
「難思の弘誓は、難度海を度する大船」との御言葉が、御師匠様の右の御言葉と重なって聞こえましたので、四つの部分に分けて書いたのです。苦労はつきもの。苦難を受けてゆけるのは名号不思議力。ぴたっと符節を合わすが如くきこえるのです。この第四信では難度海という内容に入ってゆきます。難度海という内容については「王舎城の悲劇」をあげ、その悲劇の中心人物である韋提希夫人が、お念仏によって救済されたという、極めて具体的な実際にあった出来事を載せておられます。
真宗の教えをうけられる方は、この物語りは何度も耳にされた筈です。私はお寺の経営する幼稚園にいっていましたから、大体のお話はきいており、幼稚園から帰って母に「ビンバサラ王、イダイケ夫人、アジャセ・・・・」と、きいたことを話しておりました。今でも、母はそのことを語りぐさの一つにしております。
話としては、学苑に入れて頂いて以来、何度聞き何度口にしたか分かりません。でも本当はきこえておらなかったのです。
ある時、お師匠様が名ざしで申されました。
「大石さん、提婆も阿闍世も、自分だと分らんと教行信証は、一語も読めませんよ。」
御承知の通り提婆は釈尊の教団をのっとろうとして阿闍世をそそのかせ、釈尊を亡きものにしようとした人物です。佛体から血を流し、正法を誹謗した代表的人物となっております。阿闍世は王位を奪う為、父王の殺害を計り、それをかばった母を牢に幽閉し餓死を迫りました。五逆罪を犯した代表的な人物です。
その提婆も阿闍世も自分だと知れと申されるのです。はい、そうでありますと言えるであろうか。大事に、大事にして来た自分です。一寸欠点を言われても、腹を立て言い訳をするような者が、自分の一生台無しにするような事が思えるだろうか、言えるだろうか。
私はこの段に移ってゆくとき、ここは軽々しいことを書いてはいけない。唯の説明なら書かない方がよいと心に問いかけ、その準備をしました。韋提希は世に滅多ない苦境にあってその苦しみの底で、救いを得られたのです。聖人様はこの事件を「権化の仁、斉しく苦悩の群萌を救済し、世雄の悲、正しく逆謗闡提を恵まんと欲してなり」とお受けとりになっておられます。御自身を逆謗闡提の輩と申され、王舎城の悲劇に登壇してくる人物は、逆謗闡提の私を救うて下さる為に、佛様が方便されて、即ち手段をめぐらされて、一人一人の人物に現れて、私を救う大活動をして下さったのであると。
韋提希は、王妃として恵まれた境遇にあった時も、聞法をしていたにちがいない。その韋提希が共に聞法していた主人から引き離され、最愛であった筈の我が子から、思いも初めぬ仕打ちを受けた。かねてかしづかれた家臣や腰元からも遠ざけられ、しまも餓死を迫られた。このことを「権家の仁」と受取られた聖人様のことを思います。
聖人様御自身御流罪にあわれました。ともに聞法された住蓮、安楽は死罪、松虫、鈴虫という宮中の女官も死罪。配流地の越後の御生活。教行信証を大体御完成された常陸の国では、現に板敷山の弁円による法難、日野左衛門にまつわる出来事等を心にふんまえて、それを王舎城の出来事としてお述べになられたのであろう。京都へ御帰洛遊ばされても、御本典の各所を添削されたとききます。その最後のところに御流罪になったいきさつが出ております。
「主上(しゅしょう)臣下、法に背き義に違し、忿(いかり)をなし怨(うらみ)を結ぶ。これによりて真宗興隆の太祖源空法師(ほっし)、並に門徒数輩(すはい)罪科を考えず、みだりがわしく死罪に坐(つみ)す」
この御本典の中には殆ど聖人様が、人間的な、生の感情をお出しになっておられませんが、ここには全身でもって当時のことをぶちまけておられます。眼の前に御所を、叡山を見、その看視下でです。
世を捨てられた方が得られたお浄土だ。人生を捨てられた方が、この世を越えられた如来に遇われた。浄土に往生されたからこそ、過去のいまわしい出来事が佛様の大悲の御活動と拝まれた。その御言葉をこの世のことに執着しておる迷いの世間智で以てお聖教の一句、一語を受取ろう。そういうことが出来る筈がない。分る筈がない。
「提婆も阿闍世も自分だと分らなかったら、この教行信証は一語も読めませんよ」
この御師匠様の御言葉が始めて生きてきこえてくださったのです。どういうようにきこえて下さったのか。
私が分った己れは、悪人といっても人の上に居座って高いところにいて、口だけが悪人というておるのです。一寸人から批判されるとすぐに言いわけをする。下におりたくない。上におりたい。もともと上におるのです。一度も下におりたことはない。それが真宗の教えをきくのですから分る筈がない。わたくしがきくのです。悪人という物知りになるだけです。人の下どころか、はるか上のあがっておるのです。こんな心できいて分る筈ないぢゃないか。聞法の心の方向がちがう。教えを聞かせていただいているうちに、きき方からもう迷うておると教えて頂きました。そういう中で、とつおいつしている時、画期的な出来事にであいました。そのことについて一言触れます。
ある時期、ある方と小生宅で生活を共にしていました。何回か刑を受けられた方とだけは紹介させて頂きます。後の話が分りかねるでしょうから。
「許されるなら拝む気持ちで預からせて貰います」と御師匠様に申し上げました。ある期間が経つと、又とび出してあやまちをくり返します。出所後又迎えにゆきます。そういうくり返しの後で、御師匠様に申し上げて家で生活をともにしたのです。その時は、私は教える立場でありました。人を教え得るという教育者の立場に立っておりました。救うて貰わねばならぬのは私でなくて彼だったのです。口では、食事をすすめ、入浴も先にすすめ、仕事をしても心は常に自分が上におって、教えてあげ得る立場におりました。
ここに気づかされて、私は彼の前にぴたりと手をつかされました。形ではありません。自分の業の前に手をつかされました。業と一つになったという方が適切かも分りません。このことを知らせて下さる為の彼だったのか。三十年にわたる彼との因縁は、私にこのことを教えて下さる為の佛様の御手廻わしであったのでありますか。私は、そのことから開けて下さった光明の天地を仰ぐ時、人間に生れたのは、このこと一つを聞かせて頂く為であったと、今でも深く御礼申させて頂くだけであります。すべての人の下におろされた時、自分の宿業の前に手をつかされる時、始めて広い広い世界があった。この世を超えた彼方に光明界が拝まれた。どうしてそういう世界が信じられるようになったのか。提婆も阿闍世も自分だと分らされたところから開けて来たのですから、教えのおかげ、佛様の御本願がきこえるようにして頂いたからですとしか申しようがありません。
ここでは彼という言葉を使わせて貰いました。宿業の彼方に開ける世界を拝ませて頂いた上からは、私にとってかけがえのない佛様の御化身でありました。「権化の仁、斎しく苦悩の群萌を救済し」との御法語が生きてきこえるようにして下さった。苦悩の群萌とは、聖人様は御自身のことと頂いておられます。そういう風に頂けるのは、この世を超えておられるからこそ。王舎城の悲劇の登場人物を佛様と拝まれたのでしょう。
「親鸞は弟子一人ももたず候」これは歎異抄の中にある御言葉です。教育者という立場におられません。同時に御和讃が思い出されます。
「是非知らず、邪正もわかぬこの身なり
小慈小悲もなけれども 名利に人師をこのむなり」
人師を好むと申されますのは、それを捨てられておるからこそ申される、ざんげのお心からと拝されます。
私は佛様の教えをきく力も、受取る力もない。あるのは邪見と憍慢だけ。それを教えて下さる御力が教えの方にあったのです。しかしこの事は余程のことでないと受取れない。我が力では受取ることは出来ない。何故か。大事に大事にして来た自分を根底から、台なしにされるのですから。ですけれどもそこにおいてのみ光明の天地があったのです。先哲が「かく申されました」と知っていてもそれでは助かりません。「冷暖自知」直接触れねばならない。
自分より悪人はおらぬと知らされるところは闇黒です。その闇黒の中にこそ光明の天地が開けるのです。それは「分りました」という人間の意識を通してうなずくのではない。むしろ、その「我」という意識を消して下さるのです。この光明は「我」という意識を消して下さる。今まで大事にして来た「我」を根底から迷い、幻影と知らせて下さいます。消して下さるなら、もうここで何も言うことはないではないか。でありますから、御聖教の御言葉を頂きまして、難思の弘誓、不可称、不可説、不可思議の功徳と申されます御言葉をそのまま頂きます。
この第四信を書かせて頂くにつきまして、軽々しく筆を運んではいけない。総序文の最初に、悪人正機という真宗の根本の教えが述べられておりますが、悪人ということも、始めは私は出ませんでした。どうしても心と口が違うと自分で思えるからです。始めではありません。今の今迄です。人の上におります。常に教育者の立場におります。善人です。悪人は他人(ひと)です。助からねばならぬのは他人。人をそそのかせて自分は人の頭たらんとする提婆の立場に常に立っております。人に欠点、弱点を指摘されると逆上して感情が乱れてしまう阿闍世の立場に立っております。善人です。自分を認めて貰いたい。大事にして貰いたい。大事にして貰うのが当然と自分に値打ちをつけておる善人です。
悪人が何とかなって自分を知らせて貰って人の下におりて助かろうではない。上がるも下がるもない。悪人とは自分だ。提婆は自分だ。弁円は自分だと知らされておることが光明に遇うているのです。光明に遇わせて貰っているからこそ、悪人と知らされるのです。
悪と知らされることも、佛に帰命することも、往生の大道を歩ませて頂くことも、有難いから我知らずお念佛が口に出て下さることもすべて、大悲の御本願の御廻向でございます。
「円融至徳の嘉号は悪を転じて徳を成すの正智
難信金剛の信楽は疑いを除き、証を獲しむる真理なり」
第四信を終ります。私事でございますが、この度は年賀状は一枚も書けませんでした。この紙面で新年の御挨拶を申させて頂きます。


- ひそかにおもんみれば、難思(なんし)の弘(ぐ)誓(ぜい)は難度(なんど)海(かい)を度(ど)する大船(だいせん)、無碍(むげ)の光明(こうみょう)は無明(むみょう)の闇(あん)を破(は)する慧(え)日(にち)なり。然れば即ち、浄邦(じょうほう)縁熟(えんじゅく)して、調達闍(じょうだつじゃ)世(せ)をして逆害(ぎゃくがい)を興(こう)ぜしめ、浄業機(じょうごうき)彰(あらわ)れて、釈迦、韋提(いだい)をして安養(あんよう)を選ばしめたまえり。これすなわち、権化(ごんけ)の仁(にん)、ひとしく苦悩の群萌(ぐんもう)を救(く)済(さい)し、世(せ)雄(おう)の悲(ひ)、正しく逆謗(ぎゃくほう)闡提(せんだい)を恵まんと欲(おぼ)してなり」
(御本典、総序文の最初の御文)
(難思の弘誓) 思いはかることのできない広大な誓願。
(難度海) 渡ることが難しい迷いの海、人生にたとえる。
(浄邦縁熟して) 釈尊が、浄土往生の教えを説き明かす機縁が熟して。
(浄業機彰れて) 浄土往生の行業を修するにふさわしい機類があらわれて。
(調達) 提婆提多(ダイバダッタ)のこと。釈尊の従弟に当り、阿難
の兄に当る。釈尊の威勢をねたみ、阿闍世(アジャセ)をそ
そのかせて、父王を殺害させ、自らは教団の長たらんと企て
た。
(闍世) 阿闍世のこと。マカダ国、ビンバサラ王の子。前記の提婆に
そそのかされて父王を殺し、その父王をかばった母をも牢に
幽 閉して、餓死せしめんとした。
(韋提) 韋提希(イダイケ)のこと。ビンバサラ王の妃。前記の如く、
牢に幽閉された。悶々として苦しみの中から、厭世の心を起
し、釈尊に教えを請い、救いを求めた。浄土教において、末
代の悪人、女人を救うための最初の救済者として、代表的な
重要な人物。
(権化の仁) 権化(ごんけ)とは方便のこと。真実に対す。真実に引き入
れんがために、仮りに手段をめぐらして、人を教えに導くこ
と。 仁とは御慈悲のこと。
(逆、謗、闡提) 逆とは五逆罪。謗とは正法を誹謗する罪。闡提とは一闡提、
断善根と訳す。
(世雄) 佛のこと。ここでは釈尊。
旧制中学校四年生のときのことです。私は夏休みで、郷里大竹に帰りました。ある日母が、小麦を入れた袋をかついで、隣村へ出かけます。平素私は、学校の寮にいるため、郷里を離れております。休暇はなるべく、親の膝下ですごしていました。小麦をメリケン粉にするというて出かける母について、隣村の製粉工場まで行く途中でした。
県境の川にかかる橋の中程で、母が突然、言います。
「法夫さん、あんたはお坊さんにならんね」
母は僧侶を尊く思っていたのでしょうが、当時の私はそうではありません。とっさの母の言葉に、とっさに答えました。
「あんな景気のわるい者にならんで。どうしてそういうことを言うんね」
ここまでの言葉のやりとりなら、この会話を、この紙面に載せません。続いて、母はこう申しました。
「わたしはね。あんたがお坊さんになって、わたしに法をきかせてくれて、わたしを救うてくれたらよいがと、思うのぢゃがね」
時に、母は四十六才、私は十六才。有名な偉いお坊さんになれとか、人に説教するようになれと言わなかったことが、私の心に鮮明に残っているのです。母が、産みの子の私に対して、母自身に法を説いて聞かせてくれ、そして救うてくれというのです。そのことが、心に鮮明に残っております。母も辛いことがあったのでしょう。
この手紙は、第三信です。第一信、第ニ信と有縁の方に請われるまま書き始め、書いて参りました。数は多くありませんが、それでも三十数名の方にお届けしました。私自身、御師匠様の御揮毫になる書以外は家の中に掲げていません。それだけで他に何もいらないと思うからです。皆さんも同じでしょう。だからこの手紙が押しつけになることをおそれます。
しかし、書く以上は「たとえ一頁、読んで下さっても、読んで下さる人が助かる文にしたい」―そのように願わされております。そのように思うのは憍慢でしょうか。佛様の御本願を信受し得ない私こそ、佛様を亡きものにしてきた憍慢の徒だと思えますので、力及ばずと知りつつも、この手紙を書き始めました。
そういう気持ちから書き始めましたので、第一信から、自然に
「この心は私が起こしたようでありますが、実は私が起したのでなく、佛様から、その心をたまわったのです」と書かせて頂いたのです。
聖人様は、教行信証の各巻とも最初に、「謹んで」と申されて、教も、行も、信も、証も、すべて、佛様の御本願の方で成就されてあるものを、聖人様、御自身に下さった大悲心として、謹んで頂いておられます。
第一信、第ニ信について、多くの方から、励ましの御礼状、又電話を頂きました。又、この書信の用紙にと、パックのまま送って下さった方、コピー用の原稿用紙を、これまたパックしたままを、使って下さいと届けて下さった方、器具があるからと、持ち帰ってコピーの労をとって下さる方。佛様が、いろいろな方に現れて、私を助けて下さることを実感します。
妹が昨日電話をくれました。昨日は大信寺様の報恩講で、私の家は留守にしていました。朝から何度も電話をしたといいます。
「昨日、大竹に行ったんよ。そしたらね。おばあちゃんが、机一杯にお兄ちゃんからの、第一信、第二信の手紙をひろげてね。とても、喜んで、毎日読んでおると。それは、心からよろこんでね・・・・」
後の言葉は略します。母の喜びようを早く伝えたかったから、朝から何度も電話をしたというのです。
私は電話のこちらで、はらはらと涙が、頬を伝いました。
「間に合ってよかった。母が生きておる間に、間にあってよかった」
母が喜んでくれたことをきくと、先程書きました、中学校四年生の時、私に托した言葉が、新しく甦ったのです。そして間に合ったと。
「本願に、あわせて貰ったら、すべての人にあえる。本願にあわせて貰わなかったら、親子もピッタリしませんよ。夫婦も、気持がピッタリしませんよ」と、かねて御師匠様から頂いたお言葉が思い出されます。
御師匠様は、御信心の道が明らかになられて、御両親様を、郷里へ拝みにお帰りになられました。私も、何度かきかせて頂き、その度に新しい感動を覚えました。
「よう、人間として産んで下さいました。今日は、御礼に帰りました」
と。
親子がピッタリすると申されるのは、そういうことでしょうか。そうすると、母が心から喜んでくれたのも、それをきいて涙がこぼれるのも、お念佛の中から廻向されたものだということがうなずけます。私が母を救うたのではありません。お念佛の中で、御礼の申せる心をたまわったのです。
この第三信の始めに、御本典、総序文の最初の御言葉を掲載しました。その、又、一番始めの御言葉が、
「ひそかにおもんみれば」
となっています。原文は漢字が使ってあります。
「ひそかに、以(おもん)みれば」
平素使わない文字でありますので、かな書きにしました。
この「ひそかに」という出だしの御言葉にしましても、「謹んで」と申される御言葉にしましても、佛様の御本願を、御自身に押し頂いておられる御心持が伺えます。
「難思の弘誓」については、字句の解釈として、注記してあります。
御師匠様は、一言で申されます。
「南無阿弥陀佛―ということです」と。
佛語は、いくら分析し、説明しましても、生きた、佛様の大悲心に直接、触れることはできません。ですから、字句の説明はされないで「南無阿弥陀佛は」と、申されたのでしょう。今にして思えば、お念佛を称えて頂く以外に、受取りようがないと。
「南阿弥陀佛は、大波、小波の絶えることのない人生の大海を、やすやすと渡して、彼の岸まで運んで下さる大船です」と、最初に聖人様は教えて下さいます。
「求道の友」の中で、御師匠様が書き残して下さった抜粋文を、掲載させて頂きます。二十年前、お書きになった御文です。
「親鸞様、あなたは、名号の功徳を、教、行、信、証に述べていられます。私は始めは、教と行と信と証に分類して、くわしく教えて下さいました。今はこの教、行、信、証は六字の南無阿弥陀佛と、一味一体に味了されて、私の生命となりました。ただ勿体なし、勿体なしの語につきるのであります。じっとしていられぬ躍動の姿とならされます。他力を、本願力を、称名しつつ、報謝さされます」
今から、二十年前、御師匠様の七十六才の御年の時、之程、尊い御文を頂いていたのです。しかし私は少しも味読できていませんでした。躍動がないのですから、どれ程、迫って下さる躍動の御言葉を頂いても、味読できません。佛様の大悲心の上にあぐらをかいていたのです。しかも信心を得た気になり、又得ようとしていたのです。憍慢(きょうまん)な己れの姿を知らせて頂きます。同時に、
「じっとしていられぬ躍動の姿とならされます。他力を、佛力を、本願力を、誓願力を、称名しつつ報謝さされます。」と申されるその御力が、今私に現れて下さればこそ、躍動を覚え、この文を書かせて頂いていることを思います。これすべて御廻向と頂きます。
難思とは、「人間の思慮、分別を超えておる」ということも、
「『南無阿弥陀佛』のことですよ」と、ずばり教えて下さいましたことも、もうそれだけで、何も申すことはありません。誠に、難思であります。お念佛を称えて報謝さされます。
頂いたお念佛の功徳から申し上げますと、人生の大海の大波も、小波も消えております。
「難思の弘誓は、難度海を度する大船」
聖人様の御一生、叡山二十年間、御流罪、越後の御生活・・・・私如き者が、申しあげ得るような御苦労ではございませんが、すべてを越えて来られての、御体験の御言葉として、心に届いて下さいます。
第三信はこれで擱筆(かくひつ)します。学苑の制規の最初に、在苑者の目的として、
「在苑者は、親鸞聖人の教行信証の教えに基き、自己の信仰を確立し自信教人信の実を全うすることを目的とす」とあります。
これからも、御本典の一文一文の意味を順を追うて解釈させて貰う積りはありません。一語にこもる、聖人様の御心に近づかせて頂くことを御師匠様は願って下さっておられるのですから。もし御心に触れることが出来るなら、それは御師匠様が申されました
「今はこの教、行、信、証は、六字の南無阿弥陀佛と、一味一体に味了されて、私の生命となりました」その願いが届いて下さるのです。


- 「ひそかにおもんみれば、難思の弘誓は、難度海を度する大船、無碍の光明は、
無明の闇を破する慧日なり」
旧制中学四年生のときのことです。私は夏休みで郷里の大竹に帰っておりました。ある日母が小麦を入れた袋を肩にかついで、隣村に出かけます。平素私は学校の寮にいるため、郷里を離れております。休暇はなるべく親の膝下ですごしていました。小麦をメリケン粉にするというて出かける母について、隣村の製粉工場まで行く道中、県境の小瀬川にかかる橋の中程で、母が突然言います。
「法夫さん、あんたはお坊さんにならんね」
母は僧侶を尊く思っていたのでしょうが、当時の私はそうではありません。とっさの母の言葉に、又、とっさに答えました。
「あんなに景気の悪い者にならんで。どうしてそういうことを言うんね」
ここまでの言葉のやりとりなら、母との会話をここに書きません。
続いて母が申しました。
「わたしはね。あんたがお坊さんになって、わたしに法をきかせてくれて、わたしを救うてくれたらよいがと思うのじゃがね」
時に母は四十六才、私は十六才。有名な偉いお坊さんになりなさいとか、人に説教するようになりなさいと言うたのではありません。母が産みの子の私に対して、母自身に法を説いて聞かせてくれて、そして救うてくれというのです。そのことが心に鮮明に残っております。母も辛いことがあったのでしょう。
昨日妹が電話をくれました。昨日は大信寺の報恩講で私は家を留守にしていました。朝から何度も電話をしたといいます。
「昨日は大竹へ行ったのよ。そしたらね、おばあちゃんが机一杯にお兄ちゃんからの手紙をひろげてね。とても喜んで、毎日読んでおるのと。それは心からよろこんでね・・・」
母の喜びようを早く伝えたかったから、朝から何度も電話をしたというのです。私は電話のこちらで、はらはらと涙が頬を伝いました。
「間にあってよかった。母が生きておる間に、間にあってよかった」
母が喜んでくれたことをきくと、先程書きました中学校四年生の時、私に托した言葉が新しく甦ったのです。
「本願にあわせて貰ったらすべての人にあえる。佛様の本願にあわせて貰わなかったら、親子もピッタリしませんよ。夫婦も気持がピッタリしませんよ」と、かねてお師匠様が申されたことが思い出されます。
お師匠様は、ご信心の道が明らかになるとまず、この世でいうたら先祖のご恩が思えるようになると申されます。ご家族をつれて郷里の大崎島へ、ご両親を拝みにお帰りなられました。
「ようこの世へ人間として産んで下さいました。今日はお礼に帰りました」と、合掌、畳に頭をつけて拝まれたそうです。ご両親様は無言。唯、涙だった由。お父上は寺子屋から村の学校になり小学校長を一代なされたときいております。
親子がピッタリすると申されるのはそういうことでしょうか。そうすると母が心から喜んでくれるのも、それをきいて私も涙がこぼれるのも、この世のでき事についての悲喜の涙でなく、お念仏の中からおのずから廻向されたものだということがうなずけます。私が母を救うたのではありません。お念佛の中から、私の意識を超えた、はるか彼方からの佛様の御もよおしとうなずかされます。
かねて長男が申します。
「僕は勤めておるからなかなか法座にまいられん。大事なことを書き残しておいて頂戴」
何度かきいたことですが、「そのうちに」と言い逃れて書く気になれませんでした。この度書かせて貰おうという気になって、この「第一信」を書くべく原稿用紙に向いました。さてどのようになりますか。佛様の前に座らせて頂いている謹しむ心であります。佛様の教えをどのように頂き、日常生活の上にどのように、希望となり、力となり、光となって働いて下さるか、それをできるだけ身近なところに味わいつつ、またお届けしなければいけない。それを願わされます。この気持ちも、私の考えを超えた、遠き彼方からの御本願の御働きをこい願う気持ちであります。
冒頭に、教行信証の総序文の最初のお言葉を掲載しまさいた。
「ひそかにおもんみれば」 原文は「密かに、以みれば」となっていますが平素使わない文字でありますから、かな書きにしました。
「親鸞聖人は、本文の各巻の初めに、すべて「謹んで」という御を冠しておられます。「ひそかにおもんみれば」のお言葉も同じ御心持ちでしょう。佛様のご本願を、ご自身に押し頂いておられるお心持が伺えます。
「難思の弘誓」については字句の解釈はいろいろできますが、お師匠様は一言で申されます。
「南無阿弥陀仏ということです」
佛語は、いくら分析し、説明しましても、生きた佛様の大悲心に直接触れることはできません。ですから字句の説明はされないで「南無阿弥陀仏は」と申されたのでしょう。今にして思えばお念佛を称えて頂く以外に、受け取りようがないと。
「南無阿弥陀佛は、大波小波の絶えることのない人生の大海を、やすやすと渡して彼の岸まで運んで下さる大船です」と、最初に聖人様は教えて下さいます。
聖人様がこの教行信証を大体完成されましたのは六十才までと申されますが、それまでのご一生は、叡山二十年間のご修行から、法然様の門下生になられ、ご流罪、越後のご生活、関東の二十年間、数々の法難、それをすべて超えて来られてのご体験のお言葉ですから、最初の一句からして、心に届いて下さいます。
「在苑者は親鸞聖人の教行信証の教えに基き、自己の信仰を確立し、自信教人信の実を全うすることを目的とす」とあります。
これまでも有縁の同行さんから、お便りを下さいねと言われました。少し詳しくご信心のことを書かせて貰おうと思うと長文になり、誰にもということになりません。同文になりますが、コピーしてお届けしたいと思います。
聖人様は、教も行も信も証も、佛様の大悲のご本願から私に廻向された、たまわりものでありますと申され、それを謹んで頂いておられます。そのお心が頷けるには、私自身、ご本願をそのように頂かなければ聖人のみ教えを信ずるということはできません。
如来様のご本願は、この私の為に建てられたのでありました、と信じられるようになったのは、この「私」が何一つ本当のことが分っておらぬ愚か者、このことが信じられるようになってからです。そもそも、佛様の仰せは「分りました」「信じます」と申せるようなものではなかった。私の力の及ぶところではない、私の無知、無能を知らせて下さるのと、佛様の光明に照らしだされるのは同時だったのです。己の愚かさを知らせて貰って、そのように自覚して助けて貰う。そんなことではないのです。己れの無知を知らせて頂いていること、そのこと自体が佛様の光明の中にあったのです。その光明を佛様の御智慧と申されます。
「無碍の光明は無明の闇を破する慧日なり」
この光明に遇わせて頂きますと、この光明は果てしなき久(いにし)えより、私を照らし続けて待っておって下さった。そのように思えるのです。そのお心に気ずくのを御本願をしんずると申し上げますなら、この信ずる心も佛様の方から恵まれたものでありまして、決して私が「信じます」というものではない。己れの無知、底下の凡夫の自覚の中からそういう世界が開けてきました。
同じ中学四年の夏休みにあったことです。午後三時頃、朝鮮(今の韓国)の婦人が醤油を買いに来ました。母の応待の言葉が耳に入りました。どうでも前回の代金を払ってないようです。今回もお金をもって来ないらしい。
「あんた、お金をもっておいで。もって来たら売ってあげるけえ」
対手の婦人は空の一升瓶を抱えて押し問答です。
「今度必ず持ってくるから売って下さい」
思案に余って母は、少し離れたところで下駄の修繕をしていた父のところへいって相談します。
「うちも商売じゃ。金を払わん者には売られん」
大きな声で対手の婦人にきこえるように怒鳴ります。
「あんたね。だんなさんが金を持って来んさい」そばへ引っ返して母がとりなす。
「今から帰って来たら夕飯に真にあいません。一里半もあるのです。今度来た時必ずお金を持ってきますから、奥さん。売って下さい」もう哀願です。
意を決した母が
「それじゃ、わたしが売ってあげるけえね。今度必ずお金を持ってきんさいよ」
父に承諾を求むる如く、挑戦する如く、婦人から一升瓶を受けとると醤油倉へすたすたとゆきました。
婦人が帰ったあと、しゃがんでいた父が立上るなり母のそばへやって来ました。
「わしが売るなというたのに、なぜ売ったか」言うなり、母の頬をなぐりました。末の妹が父にかけよって抱きつきました。十才ちがいですから六才です、必死で。
「お母ちゃんをたたいちゃ、いけん」
私は休暇で郷里に帰っているのです。平素離れている家庭の温もり、両親に愛情に浸りたい、その安住の場所でこういう出来事がありました。夕食後、涼み台に坐ってそのことを考えております。いろいろの話がでる中にも、そのことが頭から離れません。九時すぎて私一人涼み台におると、炊事の後かたずけを済ませた母がやってきました。二人だけになったので、私の方から敢えて口を開きます。
「お母ちゃん、今日は辛かったよ。あんなことがなければよいのに」
父を責めるでもなく、母を責めるでもなく、母に訴えます。
母は、浴衣を着て坐っている私の膝に、がばっと泣き伏します。ややあって頭をあげて申しました事は忘れ得ません。
「法夫さん、今日あったことは今日だけのことで起ったのではないのよ。昔から、こういうことが起る原因があったのよ」
十六年間養育をうけた両親です。尊敬しているのに、何故父が母をなぐらねばならないのか。悲しみをもっている子の膝に母がなき伏します。この気持ちをどこへもっていったらよいのか。自分は絶対、人をなぐることはせんぞ。解決ではなくて、その時の精一杯の抵抗でした。
同じ夏休みに母が私に申したことを先に述べました。
「お坊さんになって、私に法をきかせて、私を救うて頂戴」母は佛法をきかせてもらっておったから、宿業ということは知っておったのでしょう。この出来事は、少年期から青年期に移り変る頃に、私の心にこびりつきまして、「母が救うて頂戴」と言った背景となったのです。
それから十年後、真宗教団、今の学苑において頂くことになりました。最初に教えて頂いたのが「汝、自己を知れ」です。
右のことは一つの出来事です。「汝、自己を知れ」という内容に入って、何年もかかってこのひとつ、宿業ならどうにもならんということを教えて頂きました。父もどうにもならんのだ。母もどうにもならんのだ。それをなんとかして貰おうと思うて迷う私の宿業を知らせて下さる為の父のご苦労、母のご苦労であった。私もこの時代に生を受け、この生活の、この暮し、どうにもなるものではないと知らされてから、お念仏がきこえて下さいました。「難度海を度する大船」として。


- 私がこうして手紙をさし上げる形で文を書き始めたのは、その動議があるのです。有縁の方から手紙を下さい、待っていますと申されたことが直接の機縁ではありますが、も少し深いところから心の底に流れておるものがあったのです。私は僧侶になりましても、口ではお念佛を称えておりましても、心の底から有難いとは思えなかったのです。でありますから他のお聖教も、あの手紙の文体で書かれました蓮師の御文章も味いがありませんでした。「末代無智章」の御文章を前講の席で、御讃題に頂きなさいと御師匠様が申されましたので、ある時期毎席拝読させて頂きました。あとで御部屋に呼ばれまして、「末代無智章を毎度拝読しておるが、あんたはあれが分っとるんか」と申されました。私は味わえるどころか、不安一杯の頃でありますから返事の申しようもありません。返事をしないわけに参りませんから「分っておらないのであります」とお答えしました。もうそれから何年経ちましたか。この度、手紙を下さいと申されますお方に対して、この文を書かせて貰う気になったのは、このような生きる道も分らない私の為に、佛様が南無阿弥陀仏という本願を建てて下さったおいわれを聞かせて頂いたからです。聖人様が御本典の総序文の中で「・・・・行に迷い、信に惑い、心くらく、識(さとり)すくなく、悪重く、障り多き者、特に如来の発遣を仰ぎ、必ず最勝の直道に帰して、専らこの行に奉(つか)え、唯この信を崇めよ」と申されました。この御言葉は私にたまわった御呼びかけの御声ときこえるようにして頂いたからです。このことは、第一信の中で書かせて頂きました。このことは、御信心の道において、根本的に大切なことなので、重ねて書かせて頂きます。第一信において「如来様の御本願は、この私の為に建てられたのでありましたと、信じられるようになったのは、『この私』が何一つ本当のことが分っておらぬ愚か者、このことが信じられるようになってからであります」と書かせて貰いました。初信から、突然こういうことを申し上げましたのは、こゝが分りませんと御信心は開けて来ません。末代無智章を何度拝読しても「拝読」していないのです。眼で字を追い口で話をしましても味読できませんから、喜びもないし 「あなかしこ」と口先だけ。御師匠様が「どうなろうにゃー」 話しをさせてやらねば御信心は進まんと、話をさせてみれば、少しも心に響いてこないし、やるせない御気持ちから尋ねられたので「私は分っておらないのです」と。今思えば、何が分っておらないのか分っておらんということが、分っておらなかったのです。生きてゆく道がないのです。人に会えば、話もします。でもどのように生きていったらよいのか、信念がありませんから、このことを行に迷い信に惑いと私のことときかせて下さいました。そういう心は暗いです。原文では心昏くとなっています。昏迷の昏です。人生の道に、はたと歩みが止って、さてどちらに進んでよいか、陽は沈んで了って、どの道へいってよいやら、その道も先があるのかないのか、昏迷とはそういう心持でしょうか。この聖人様の御言葉は、御自身のことを申されたのでしょうが、読ませて頂く私にしては、私のことを、私が知らないから、私に代わって言うて下さったのです。そのように信じられるようにして下さったのです。
私はこの書信を始めたのは、長男が以前より大事なことを書き残しておいて頂戴と申したことが直接の縁でありました。この第二信の始めに「もう少し深いところから心の底に流れておるものがあったのです」と書かせて貰いました。それは何であったのかを伏せたまま、筆を運んで来ました。聖人様がそのことを既に申しておられるのです。「行に迷い信に惑い、心くらく・・・・・」特に如来の発遣を仰げ、これは最勝の直道であるぞと。直道とは、直ちに救われるという意味もございましょうし、佛様が、直接、人をつかわされるのでなく、直接救うて下さるという御心持も伺えます。発遣とは、さしむけるということです。阿弥陀佛が、釈尊をこの人間世界に発遣されて、即ちさしむけて下さったのでありますと、聖人様は御自身に受取られたのでしょう。御自身は行に迷い信に惑い、この世で、どのように生きていったらよいのか分からない、あるのは悪重く、何につけても悪い方に考えて、見ても聞いても障られるばかりの者でありますと御自身のことを申されておられるままが、阿弥陀様が釈尊を発遣されて、最勝の直道である、大経のお声を直受されておられる姿と拝します。その大経は、常々おきかせ頂いておる通りです。あの上下二巻の経典は、詮じつめれば「弥陀の本願を説くを経の宗致とす。名号をもって経の体とす」と聖人様は頂いておられます。ですから、最勝の直道に帰しと申されますのは、大無量寿経という、末代の凡夫が、直ちに救われる大変勝れた経典に帰し教えに説かれてあるように本願を信ぜよ、そして名号を称えよ、それで間違いなく往生するぞ。ゆめゆめ疑うな。いや疑いがなくなると。お前に疑うなと要求などしない。お念仏は御礼になる。唯御礼になる。そうしてお前が助かって、生死流転の中にあり乍ら、心から安心して毎日この世から浄土の旅をしてくれるようになったら、佛様の方が安心する。その御本願のままに救われたお心を、総序文の次の御文に「誠なるかな、摂取不捨の真言、超世希有の正法・・・・」と申されたのでありましょう。こうして、私は何も分からなかったのに、こういう私の為に誓われた大きな御心があったことが信じられるようになりましたのは、御師匠様の切なる願いが御化導を通して、届いて下さったからでありまして、信じられるようになってからは、私の心の底に、佛様の御本願と申し奉る偉大な御魂が常に流れて下さるようになりました。
そしてその御本願は年々、月日とともに、はっきりと力となり、喜びとなり、光となって現れて下さって、もう御念佛以外に何も要りません。御名号の中に何も彼も御成就して下さっておられて、私の生命となり血肉となって下さっておられることを私は、また御名を称えて御礼申させて頂くのです。仏様を離れては生きておられないという気持ちも、私が思うのでなく、お念佛に摂取されますと、広々とした世界が見えて参りますので、暗かった過去の迷いがはっきりと分ります。あれでは苦しかった筈と分ります。「心昏く、識すくなく、悪重く、障り多きものは、益々、しかもはっきりと、それは私でありますと知らされますし、知らせて下さったのが、佛様の光明のお照しのおかげでありますから、もう迷いの世界に戻りません。唯念仏せよ、専らこの行に奉えの御呼び声を頂くのであります。
「大事なこと」と申しますと、もうこのこと以外にない。少しくどくどと長文の手紙になりましたが、こらえて下さい。
私が重ねて申し上げたかったのは、入苑当初御師匠様から頂いた御言葉です。「汝、自己を知れ」 このことについて、屡々、きいて頂きました。「大石さん、あんたは、私に始めて会うた時、あいたい人に始めてあわせて頂きましたと言うたのう。本当は、あんたはわしに会いたいのではないのでよ。あんたは、あんた自身にあいたいのでよ」 その時は、勿論、結婚もしておりませんでしたし、子供も生れておりません。子供が、大事なことを書き残しておいて頂戴と申します。その大事なことを、子供の出生以前に、私は師からきかせて頂いていたのです。そして後に知らせて頂いたのですが、この御言葉は、大経の始めに説かれておりました。法蔵菩薩が、師佛に対されて「広く教えをお説き下さい。私は教えによって修行し、佛となって迷いの衆生を救いとりたいと念願しています」と。それに対されて師佛が、お答えになっておられるのが、「汝自当知」 汝自ら当に知るべし。 外に探し、求めても救いはないよ。自分というものはどういう人間か。なぜ苦しいのか、不安なのか。不安の根源を、人が悪い、世の中が悪いと外に求めても解決はつかないよ。心の欲が無限だから。満足する時は、絶体に来ないぞ。それならどうしたらよいのか。この大経の根本命題を自ら説かれて、人間が本当に遇いたいのは、弥陀の本願である。その御本願に遇われた釈尊が、法蔵菩薩の願として、自らの中に開けた尊い世界を紹介され、そういう世界に是非、衆生を迎えて、幸福になって貰いたいという自らの中に発起された願いを法蔵菩薩の願としてお説きになりました。人間釈尊は、肉体はこの世から去っても、釈尊が感知された弥陀の御本願は、人間あらん限り活動は止むものでない。この願いは、一人として救われない人間がこの世にある限り、我は浄土で安閑としておれない。迷える衆生の心に入って、共に迷い、離れたら衆生が助からんから、寸時も離れたまわずに呼んで下さっておられるお心を、人間の分る言葉として大経の中に御本願として説いて下さいました。大経を頂きますと「汝、自ら当にしるべし」 法蔵菩薩が師佛の御化導に依って、本当の自分を発見された、即ち御自覚遊ばされたら、この肉体を亡びても、本当の自分はこの天地の底に流れておる偉大なる御力から現われたものであった。釈尊は、永い御修行の果てに、闇黒の中から、この御力に眼覚められた。その御力は、迷える凡夫にこの御力の働いていることを知らせてやりたいと願いをもっておられる。その御力は広々として明るい。この御力はすべての隔て対立を超えておられる。これは光明だ、これを無量光と名づけずにおれぬ。そして、このみ力は、人間あらん限り、働き続ける。我が肉体は滅するもこの御力は、死し給わず。これは無量寿の徳をもっておられる。釈尊は、我が心に御自覚遊ばされた不可思議なる大霊に対峙されてじーっとその御徳に不思議さに打たれた。そして、人間悉陀太子が、釈迦牟尼佛と生れ変られた。肉体は同じ人間であっても、自覚者となられた。本当の自己を知られた。そして私達に対して、汝は汝を知っておらんで苦しんでおるのだ。汝は汝が思っておるような肉体に執われ、迷うておる粗末な人間ではないぞ。もっともっと尊い人間であるぞ。これを、教えて下さる為に、御師匠様が「自分に遇え」と教えて下さったのです。
聖人様が、御本典総序文の終りに「慶ばしき哉や、西播月氏の聖典、東夏日域の師釈に遇い難くして今遇うことを得たり。聞き難くして、已に聞くことを得たり」と申しておられます。自己に遇うということは一面においては、己れの助かりようもない迷いの凡夫を知ることであり、その者のためにお前が本当に遇いたいのは、佛様の御本願に遇いたいのぢゃ、わしに遇うたら、必ず、このようになりたかったのですと満足して喜ぶぞ。その確心がないのに、何故わしはお前を救うという願を述べるものか。一寸でも救済するに、ここは力不足という危ぶむものがあったら、十方衆生と呼びかけ得るわけがないぢゃないか。この切々たる御本願に遇わせて頂いて、心に疑いが晴れ、大満足して今度は、そういう世界があることを知らずに、以前の自分と同じように悩んでおる人を又浄土へ迎えてゆこうという願いに生きるようになったのを自覚者と申される。こうなって始めて、師釈のおかげで、自分を知らせて頂きました。御本願に遇い難くして遇わせて頂きましたとなられたのでしょう。御師匠様から、最初に「汝、自己を知れ」という御言葉を頂き、爾来何十年、このことが聞こえるようにして頂いた御恩は謝し難い御恩で、今、こういうことを書かせて頂いているのも絶えず呼んで下さっておられるみ佛の願力を頂いているのです。御佛様を讃える力も、み佛の御働きあればこそです。これを、第一信で、「御廻向」と述べさせて頂きました。第二信は、これで終ります。少し長くなりましたが、大事なことは、「佛様の教え」このことは常々御師匠様が申されました。「この世で一番、大事なのは人間である」 凡夫は物や金を大事にする。金をもうける為に、人間を使う。役に立たぬと思ったら捨てる。人間なくして何の金ぞ。何の学問ぞ。地位ぞ。だからわしは人間を一番大事にしている。わしは人生の価値、根本価値がはっきりしているのぢゃ」 更に「教えが信じられるのは、人間である。教えが信じられるようになって始めて、人間は佛様によって救われる可能性のある人間だから、佛様が人間を大事にされるのである。佛様が信じられるようになると、人間を尊び、大事にするような心を下さるのだから、この世で一番大事なのは教えであります」と断定されました。その人間の一人である私が、御師匠様の御化導によって、自分を知らせて頂いたのです。でありますから、縁ある方から「大事なことを書いて下さい」と申されましても、御本願をきかせて頂いて信じ奉る身となる以外に、もう外に何も、私の方にはないのです。私も聞かせて頂いたことを喜ばせて頂き、又、御本願の御働きのままに語らせて頂き、動かせて頂くだけです。
いざ書かせて頂くとなりますと、「教行信証をこのように頂かせて頂いております。このみ教えは、私を助けて下さる為に、阿弥陀様が親鸞聖人を和国に発遣されて、浄土真宗をお広め下さったのでありますと、このことに自然に筆が向いて来るのです。従って佛語も出ます。なるべく難しい佛語は使わないで、だが御精神を失わぬように書き現わしたいとなっても、原文の御言葉は時に書かせて頂きます。そして真宗のみ教えをうける上は、やはり御本典は、拝読して頂きたい、始めからは味読はできないでしょうが、私はこの聖典が頂かれないのは余りにも勿体ないと思います。第二信を終ります。


-
お別れして一週間経ちました。この前、御法座でお会いした時、「また手紙を
下さい」と言われたことが心に残っております。以前から有縁の同行様から同じ
お言葉を頂くのです。そのお言葉にひかれて、折に触れ、心に感ずることを書い
て、お便りをさせて頂いておりました。
けれどもはがきでは意を尽くさぬことが多いし、少し詳しく教えに触れてゆきた
いと思うと長文になって、どなたにも差し上げることが出来ません。そういうこ
とから、私は考えまして、コピーにして、同文であっても読んで頂こうと思いた
ちました。
このことについて、申し上げたいことがあります。親鸞様が「謹んで真宗の教
行信証を案ずるに如来大悲廻向の利益なり」と仰せられております。御本典の証
巻の終りにあります御言葉です。聖人様は、佛様の教えをきくことも、信ずるこ
とも、お念仏を称えることも、大悲心に救われて生活することも、すべて佛様の
方からさせて下さるので、私の力できくのではない、称えるのではない、すべて
佛様からの賜りものであると申されるのです。言葉で申せば、一口ですぐ申せま
すが、このことが真宗では、根本的に大事なことでありました。これから回を重
ねてゆくにつれて、それに触れてゆくわけでありますが、実は私が、このよう
に、同行様に書かせて頂こう、お便りをさせて頂こうという心も、私が起こした
ようでありますが、実は私が起こしたのでなく、佛様からその心をたまわったの
です。そのことを最初に申し上げたかったのです。この、佛様の方から下さると
いうお心を、真宗では御廻向と申されます。
御本典(教行信証のこと)教巻の最初に「謹んで浄土真宗を按ずるに二種の廻
向あり。一つには往相、二つには還相なり」とあります。聖人様が浄土真宗とい
う御宗旨を私達に紹介して下さるのに、最初からずばりと「廻向」というお言葉
を使っておられます。そして「証巻」の終りのまとめのところにも、先程書かせ
て頂きました御文を述べておられます。「真宗の教行信証を按ずるに如来大悲廻
向の利益なり」と。
この廻向ということを最初からきかせて頂いていたのですが、さっぱり分かり
ませんでした。勿論始めから頷ける筈はないわけでありますが、私と同じ疑問を
もっておられる方があるかもと思いますので、このことについて一言述べてみた
いと思います。
廻向という字は「えこう」と読みますことは、今あなたに申さなくても御承知
のことです。この意味を字典で調べてみますと、次のように説明されています。
「廻転趣向の義で、此方のものを、彼方へふり向けること。これに自力の廻向と
他力の廻向の二つがある・・・・・」説明をきくとすぐ分かるのですが、分ると
いうことと信じられるということとは、全然ちがいます。聖人様は御廻向という
御言葉をどのように使っておられるかを伺いますと、教も行も信も証も、如来様
の大悲の御本願から私に廻向された、たまわりものでありますと申され、それを
謹んで頂いておられます。そのお心が頷けるには、私自身ご本願をそのように頂
かなければ、聖人の御教えを信ずるということはできません。
このお便りの初めに、「お便りをさせて頂こうという心も、私がおこしたよう
でありますが、実は私がおこしたのではなく、佛様からその心をたまわったので
す」と書きました。そう書きますと、唯の言葉のおきかえで、自分の救済とどの
ような関係があるのかと軽く受け取る方があるかも分らんから、聖人様の御言葉
を、教行信証の中から抜粋させて頂いたのです。分かりきったようなことを重ね
て書きますと、失礼に当るのではないかと懸念されます。私も書き乍ら、大事な
ことだから、私自身へ下さる御教えとして、心に刻み乍ら書かせて頂いているの
です。
如来様の御本願は、この私の為に建てられたのでありましたと、信じられるよ
うになったのは、「この私」が何一つ本当のことが分っておらぬ愚か者、このこ
とが信じられるようになってからです。そもそも佛様の仰せを分かりました、信
じますと申せるような者では、私は、なかった。私の智情意を尽くしても、私の
力の及ぶところでない。私の無智、無能を知らせて下さるのと、それを知らせて
下さる佛様の光明に照らし出されるのと同時だったのです。己の愚かさを知らせ
て貰ってそのように自覚して助けて貰う。そんなことではないのです。己れの無
智、無能を知らせて頂くこと、そのことが佛様の光明の中にあったのです。その
光明を智慧、佛様の御智慧と申されます。その光明に遇わせて頂きますと、この
光明は、はてしなき久えよち、私を照らし続けて待っておって下さったと思える
のです。そして、そのお心に気づくのを御本願を信ずると申し上げるのでござい
ますか、そうすれば、その御本願を信ずるということも、佛様の方からの、おさ
しむけでありますか、それを御廻向と申し奉るのでありますかと、何も彼も疑問
がとけたようになりまして、そのことを境として、年々、月日とともにはっきり
してきまして、佛様ということを離れては生きてゆけないということにならせて
下さったのです。
そうならされてから、お便りを差しあげようという気持ちも、あなたが「手紙
を下さいね」と申さなかったら、さしあげようという心になりません。下さいと
いうお心は、佛様の教えを大事に思われ、懐かしまれるお心でなかったらその一
言がでません。双方の間に、佛様の御本願の御働きを感ずるのです。私はそのよ
うに思えるようにして頂いたことを感謝します。その感謝する心が自から口に出
て下さるのが、お念佛なのです。このお念佛が根本となって、私のすべての生活
が始まるのです。このようにして下さったのがひとえに、佛恩、師恩でありま
す。無上の御育てを頂いたことを感謝致します。
初信はここまでにします。
(註) このお便りは手紙文になっております。かねて、長男からも大事なこと
を書き残して欲しいと何度も頼まれました。同行さんからも手紙を下さ
い。何度も読ませて頂いておりますとも。長男はまとめて冊子にしたいと
も言います。そういう要望をうけますと原稿用紙に向っても、佛様の前に
座らせて頂いたような謹む心をたまわります。そういう心から、私が勉強
させて頂こう。そういう気持ちでこの書信を始めました。


- 故(かるがゆえ)に知んぬ。円(えん)融(ゆう)至(し)徳(とく)の嘉号(かごう)は、悪を転じて徳を成す正智、難信金剛の信楽(しんぎょう)は、疑(うたがい)を除(のぞ)き証(さとり)を獲(え)しむる真理なり。爾(しか)れば凡(ぼん)小(しょう)修し易(やす)き真(しん)教(きょう)、愚鈍(ぐどん)往(ゆ)き易(やす)き捷径(せっけい)なり。大聖(だいしょう)一代の経(きょう)、͡是(この)の徳(とく)海(かい)に如(し)くは無し。穢(え)を捨て浄を欣(ねが)い、行に迷い信に惑い、心昏(くら)く識(さとり)寡(すくな)く、悪重く障(さわり)多きもの、特(こと)に如来の発遣(はっけん)を仰ぎ、必ず最勝の直道に帰して、専ら斯の行に奉(つか)え、唯斯(こ)の信を崇(あが)めよ。
教行信証の最初のお言葉を第三信の冒頭に掲載しました。右の御文はその次に続く御言葉です。原文は漢文ですが真宗聖典には和語文になっておりますからそれに依りました。同行さん方はよく読んでおられましょう。この総序文は皆さんがお持ちの勤行聖典に読経用として載っておりますが、御本典を始めて読まれる方の為に、ふりかなをつけさせて貰いました。第一信の回向と同じように、嘉号とか信楽とか障、直道・・・・・平素は眼に触れない、耳にしない言葉だと思います。
第四信からこの第五信を書かせて貰う半月の間にいろいろなことがありました。まず新年を迎えたこと。一月七日に元天皇が崩御せられたこと。当日は法信寺の御法座の日でした。朝八時四十分にそれをきき、すぐにテレビのスイッチをひねり釘づけ。九時出発、車に乗って着くまでラジオに聞き入りました。内閣総理大臣の「謹話」も一語一語謹んで聞かせて貰いました。元天皇の御病気が報ぜられてより、その日がくることは分っておりましたから、その当時から心では申させて貰っておったことは
「永い間、御苦労様でございました」
昭和生まれの方は丸々昭和につかった人生ですが、明治生まれの方も人生の大半は昭和の中です。私は大正十年生まれですから大半どころではありません。昭和の始めより昭和の終りまでお世話になった人間です。昭和六十三年間で私の心の中心となっていることは、何といっても戦争体験と戦後の混乱期のことです。その時代に生きられた皆さんも同感されるのではないでしょうか。天皇陛下がお亡くなりになられました七日より、テレビや新聞で有識者の方々の談話が一斉に報ぜられました。昭和の回顧、大行天皇の思い出やお徳についてのお話。新天皇の素顔、皇室のあり方、天皇制のあり方や批判。どれも私たち国民の一人として聞かねばならぬことでありますし、考えねばならぬことばかりであります。語られる方は殆んど戦争を体験されております。戦後の苦しさを生きて来られた方です。ですからそういう体験をふまえての日本の未来、国民のあり方という考えが出ています。これはどんな時代だって同じことですが。
そういう動乱の戦後、私は仏教を聞かせて頂いたということが昭和六十三年間を超えて、私の人生に意味を与えて下さった中心のことでありました。仏教の中でも浄土真宗という親鸞聖人の教えをきかせて頂いたことです。
七日に法信寺にゆかせて頂いても自然にそういうお話になりました。前天皇についてはいろいろ受けとめ方がありましょうし、各自異ります。占領軍総司令官として来たマッカーサー元帥に天皇が始めて面会された時のお言葉
「私は処刑されてもよいが、どうぞ日本国民を救って下さい。罪は私にあります」
この言葉は戦後マッカーサー元帥の大戦回顧録として朝日新聞に連載されたある日の記事に載っていました。このことを御師匠様が大変喜ばれてまして、御法座で話されたのです。
「私の一切をあなたにゆだねます」となげ出された天皇を、元帥は全責任をもって守って下さったのです。
「罪は私にあります。国民を救ってやって下さい」となげ出されたお心とお言葉が、天皇御自身を救われたのです。
御在位六十二年間。数々のお言葉、御行動の中で象徴としての天皇の象徴のお言葉として受けとめたい。竹原支部、高松と廻り、十五日は大信寺と私もこの十日間御法座を勤めさせて頂きましたが、心の底にはこのことがありました。自然に御法座にもそのことが出ます。天皇もなりたくて天皇になられたのではありますまい。明治天皇は京都御所から昔の江戸城、今の宮城に移られました。明治維新となって日本の夜明けが始まったのです。天皇を迎えねば夜明けの出来ない当時の日本の情勢でした。天皇も、日本の国全体が背負わねばならぬ業の中から生まれられたのです。昭和天皇となられる前天皇も、大正天皇が病弱であらせられたから若くして摂政となられ、又若くして天皇の位に即かれました。そして日本全体が戦争に突入。天皇も日本人として生れた以上、生まれ乍らにして国の業、時代の業を背負うて出生され成長されました。国民一人一人もそういう宿業の中に生れ、そしてその時代の業で成長しました。勿論私も同じです。天皇もどうにもならなかったのです。皆もどうにもならなかった。人間が、善かった、悪かったといってもどうにもならぬ。人間の力ではどうにもならぬ大きな力の働きを思います。
七日から始まったテレビの特別番組を皆さんも見られたでしょう。聴かれたでしょう。これは妻から間接にきいたのです。外から家に帰って玄関に一歩上がった途端に妻が話し始めたのです。
「今ね、丁度森繁久彌が話しておったところよ。感動した」と。
テレビに何人かの有識者が出て、昭和の反省、思い出を語っていたのでしょう。彼は二十才代にNHKのアナウンサーの仕事で満州へいっていました。仕事の関係で到らぬところはない位。隅から隅までとび廻っていました。或時、大連で一見して日本人と分る和服を着た老人を見ました。尋ねてみると長野県出身の農家の人。孫が満州開拓団に入っているのです。再三来いと手紙がくるので会いたくてやってきました。ところが田舎の出身。言葉が分らぬ。どこをどう間違ったか開拓団とは方向ちがいの大連の街中。森繁久彌も仕事の道中だったのかスタッフ数人と同行しました。今日中にどうしても目的地に到達できません。途中で「一緒に泊まろう。そして明日目的地へ」ということになったらしいのです。そしたら、そのお年寄りが、自分は百姓だから、この国の農家に泊めて頂きたいと申し出ました。さるべき人の紹介で、通訳を介してある農家でお願いしたそうです。そこの主人が快く承諾してくれて、その時、その老人が大地に手をついて頭を下げた。
「私の孫が、あなたの国で大変お世話になっております」
森繁久彌以下スタッフの方々が思いもかけぬ成り行きに、あっけにとられたという話です。あまりの意外な姿にあっけにとられた。数ある思い出の中で最も感動したこととして語られたそうです。番組に出られた方々も、二十才代から今の森繁ぶしは始っていたのですねと。
そういうことを感動を以て語る森繁久彌の心根に感動したのかも分りません。それを聞いて又妻が語るその感動が私に伝りました。
その反対の出来事も話されたそうです。旧満州で、日本人がずい分悪いことをした例。満員の汽車の中だったらしい。現地の人が座席に座っているのをひきづり出して、自分がその席についてたばこをふかしていた。同じ日本人として恥ずかしかった。腹が立った。国家権力をかさにきて我侭、気侭をする。私もそれをきいて腹が立ちました。難しい理屈を言わず、実際にあったこと、見たことを話してこれからの日本人の生き方、在り方について考えさせてくれられました。私は有難かったです。
何の理くつは知らなくてもーあなたの国で私の孫が大変お世話になっておりますーこの生き方は、対手もこちらも共に救われる。現地の人を引きずり出して、自分が座席についてたばこをふかす。これは自ら滅亡を辿る。天地の大きな力の動きだからどうにもなりません。日本人自体がそれを憎みます。
私はテレビを見、聞きした中でこのことが一番心に残りました。おじいさんの言葉をきくと、涙が出そうになる位でした。よい話を聞いたよと妻に話した位。
戦後私は親鸞聖人の浄土真宗の教えをきかせて頂いたことが、昭和期を超えて、自分の一生の中心となる大事なことであったと書きました。その内容を申し上げますと第四信に書かせて貰った通りです。聖人様はー南無阿弥陀仏は、難度海という渡り難い人生の海を渡らせて下さる大船であるーと最初に申されました。そして具体的な例として難度海と言う内容を王舎城の悲劇に出されました。読むのは易いです。ですけれども「提婆も阿闍世も自分だとわからなかったらこの教行信証は一語も読めません」このお言葉の前にたじろいだのです。だから軽々しく書けない。救いを求めて教団に入れてもらったのに、自分の一生を台なしにするようなことが思えるだろうか。人をそそのかせて、逆上したらしてやったりと喜ぶ提婆の心。人の言葉で、頭に血がのぼって口に何を言うやら。親を牢に幽閉する阿闍世の心。いやじゃ、戦争はいやじゃと言い乍ら、事実は戦争をやっておるのが自分じゃと知れと言われるのです。そういうことが思えるだろうか。
ここに到ると私はペンをおいて、しばらく考え込みました。第四信の時と同じです。先程書きました話。座席に座っている現地人を引きおろして、自分が席に座ってたばこをふかす奴。同じ日本人であり乍ら恥ずかしく、腹が立ったのですが、誰がみても「くそっ」と腹が立つような人間「それがお前だと知れ」と言われるです。一番底下の凡夫の自覚の中に、最上絶対の世界があるのです。私に感動を与えて下さったおじいさんの姿もその中から生れます。それが私にとってお念仏の救いだったのです。
「円融至徳の嘉号は、悪を転じて徳を成すの正智
難信金剛の信楽は、疑いを除き証を獲しむる真理なり」
私は教団にありまして常時、十人前後の方と生活を共にしております。起床は年中朝五時、そして勤行、法話、体操、掃除、食事。禅宗の僧堂の生活に比較すれば問題になりません。肉食し、妻帯者です。ですけれども一応規則正しい生活といえましょう。だが寒い朝は少しでも長く寝たい。何十年続いたのだから少しは心が清浄になったか。全く反対です。そのくせ導師が御法語を拝読するとき間違うとどんな心が起きるか。提婆の心です。人を見下げます。その心は自分に値打ちをつけておる心。自分の欠点を言われると腹を立てる。その心も人の上に常に上っておりたい。私は汽車の座席に坐っておる人を引きずりおろして、そこを坐った覚えはありません。むしろ座席を譲って他人を坐らせてあげる位の人間だと思いたい。人に語りたいです。しかし人も憎む、私も憎むような、日本人として恥ずかしいと思わすような人間が実は自分なのです。
それを知らせて貰うと、実に広い世界が開けます。すべてが拝めるのです。座席を奪い取るような自己の姿の自覚の中から、人の前に手をついてお世話になりますという心が生れるので、「円入至徳の嘉号は・・・・」と申されたのでしょう。
一月十三日夜高松から帰りました。九時頃遠方の同行さんから電話がありました。そこの高校二年のお子さんが一年以上登校拒否。本人が希望しますので、学苑において下さい、そして私の家において下さいとの御依頼です。私も人生を拒否した人間です。表現が不適切なら救いから除かれた人間です。だがそこに救いがありました。仏様の方からさしのべられていたお浄土がありました。そして人生を懐しむ生活が開かれました。人をお浄土へ迎えてゆこうとする願いが起ってきました。こうして業に追われて不安な生活を今日も今日もと生きて来た私にも、生かされてゆく道をたまわったのですから、お念仏の中では私の業は転じられて、そのお子さんの業を抱いてゆく働きにして下さるのです。いわば、私の願いを叶えて下さる為にそのお子さんが来て下さるように思えるのです。私の親切心からするのではありません。御名号という仏様の御智慧より湧き出て下さる御徳を私の因縁の上に因縁としてたまわるのです。ですから喜んで引受ました。私が助けて頂くのです。どこへ行っても「お世話様になります」というおじいさんのお姿もお念仏の中から出るのです。たまわるのです。御廻向です。

真宗大谷派 普光山 長仁寺
本願道場
〒871-0104 大分県中津市三光諌山1161-1
電話0979-43-5017